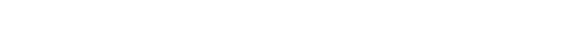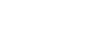「Summer Pockets」 ショートストーリー ~夏の眩しさの中で~【久島 鴎 編】
<いつかきた道>
「鍵、見つからないねぇ」
「そうだなぁ」
時刻はちょうど正午を過ぎたところだ。
いったんお昼ご飯を食べてから合流したものの、お互いこれといった妙案は浮かばないままだった。
「海神が守護するカイテイ、か」
メモのヒントを手がかりに一通りあたってみたけど、それらしきものはまったく見つからなかった。
「ねぇ、やっぱり海神って、海亀のことなんだよ。海底なんて亀にでも乗らないとたどりつけないよ」
「絶対にない」
私と羽依里はメモに残された鍵の在りかを探して、島を歩き回っていた。
「あとな、お前当たり前のように人にスーツケースを押させるな」
そう。正確には歩いているのは羽依里だけで、私はほとんどスーツケースの上だった。
いや、これはこれでけっこう大変なんだよ?バランスとか。
「筋トレ大好き羽依里君じゃないの」
「ふん。このくらいで鍛えられるか……このくらいやらないとなっ」
「おおお」
スーツケースが速度を増す。舗装されたまっすぐの道路を風をきりさいて、気持ちよく進んで行く。
私は思わず空に向かって手を広げていた。
「音速を、越えそうだよ」
「越えるか」
「と……?」
がくんと、いきなりスーツケースのバランスが崩れる。
「わ、わ、わ」
私の体はそのまま宙に放り出されて──
「危ない──」
地面に衝突した──と思った私の体は、意外にもやわらかな感触に受け止められた。
やわらかというか、ややごつごつというか。
「ぐぐ……」

下からうめき声がする。そうか、羽依里をクッションにしていたんだ。
私は羽依里におおいかぶさるように倒れていた。
「ど、どうも……ありがとう」
慌てて起き上がる。
「いや……むごっほむごっほ」
羽依里が咳き込んでいた。
「あ、ごめん。苦しかったね」
「むごっほ!」
すごい咳き込んでいる。私、そんなに重くないけどな。
「いやぁ、びっくりしたね」
「ほんとにな」
「何かにつまずいたみたいだけど……いや、これは……」
「あー! タイヤがとれてる」
スーツケースのキャスターの1つが外れてバランスを失っちゃったんだ。
「まぁ、古いスーツケースだしこういうこともあるだろう」
「困るよ……こんなの……こんな……」
私は愕然としていた。
「鴎……。おとーさんが残したスーツケースだったよな。それは確かにショックだろう……」
「ショックだよ! このスーツケースが無くなったら私は羽依里に、何で運んでもらったらいいの」
「一輪車にでも乗っておけ!」
「羽依里、一輪車の難しさ知らないでしょ。あれ、くいってなるからねくいって」
「分からん。というか多分食い違っているが、俺が言ってる一輪車ってのは荷台ついてるやつだぞ」
「一輪車が二台?? なに」
「いや、いいや……これどうしようか」
「スーツケース、どこか修理してくれるところとかないかな」
「そうだな……修理屋なんて店はなさそうだけど、それっぽいところなら相談してやってくれるかもしれないな。ちょっと知り合いに聞いて見よう」
「知り合いって?」
※※
私はその場にとどまって、羽依里が山まで友達を呼んできてくれた。
加納天善君。廃屋で卓球をしている男の子だ。
なんでも、以前動かなくなったバイクを見てくれたらしい。確かにジャージ姿は、なんとなくいろいろと修理できそうな感じだった。
「スーツケースの故障?」
やってきた天善君は私と壊れたスーツケースに少し面食らったみたいだ。
「いや……すまんが、エンジンを直すのとはわけが違うからな。これは、代替の部品がないとどうしようもない」
「そうだよな。なぁ。そういう店って心当たりないか」
「んー……。まぁ、あるとしたらあそこかな」
「どこ、それ」
※※
3人で連れ立って、商店街の一角へ向かう。
案内されたのは、『徳田スポーツ』というお店だった。
「たのもう!」
天善君が無駄に威勢の良い挨拶で入っていく。
「なんだ、お前ら。ぞろぞろと。徳田に何の用だ」
気取り顔の男の子が出てくる。
「実はこの子のスーツケースが壊れてて……」
羽依里がこちらを指さす。
「これ、ここで修理してほしいの」
「ふーん?」
徳田君?はしばらく私のスーツケースを眺めたあと、ため息を吐いて、店の奥を指さした。
「こんな古いものより、新しいスーツケースにしたらどうだ。徳田の特注品だぞ」
「だってさ」
羽依里が振り返るけど私は手を振る。
「いーやだ。かっこ悪いし」
奧に置かれているのは、なんだかえらそげな形をしたいかにも最先端でございますという感じの、青いスーツケースだった。
「なんだその女は。お前、徳田のクオリティを舐めるなよ。お前が乗ってもびくともしないコスモナイト製だぞ」
「徳田クオリティなのかコスモナイトクオリティなのか、どっちだ」
「お前が乗ってもってなによ。そもそも私はそんなに太ってないですわい。行こう。不愉快だよ」
「ふゆか……っ!? いいだろう! そこまでいうなら20万のところを半額にしてやる。女心へのサービスだ」
「こりゃダメだわ」
「ダメだな」
「お、おい。お前ら、何が気に入らなかったんだ。このクオリティが目に入らないか」
「悔い改めろ!」
私は指を指して叫んでいた。
「くい、あらた……」
呆然とする徳田クオリティ君を置いて私達は出て行く。
※※
「やれやれ。女心が分からない奴だな」
「まったくだ」
「まったくだよ」
「よりにもよって青のスーツケースはないよな」
「ないよな」
「え?」
「男にピンクのスーツケースを勧めたら気を悪くするのと同じだな」
二人してうなずき合っているけど、私が怒ったのはそこじゃない……。
「しかし困ったな。スーツケースの修理……すぐには思いつかないな。なんといっても部品がないことにはな」
「そっか」
「力になれなくてすまない」
「いや、いいよ。ありがとう」
「ありがとうございます」
私と羽依里は天善君に頭を下げる。
天善君は山へ帰っていった。
「どうする? 修理は難しそうだが……」
「ううん……やっぱり、探そう」
「新しいスーツケースってのも手じゃないか?」
「ダメ。これじゃないと」
「そっかよ。けど困ったな。地元の人間でも心当たりがないんだから、見つからないんじゃないか」
「のんのん羽依里。島の人達が知らない海賊船を探している私達が、修理屋さん程度を見つけられなくてどうするの」
「わかるようなわからないような理屈だな……」
「ね、ね。こっちとかありそうじゃない」
「ありそうか? お前、体力大丈夫か?」
「大丈夫だよ。れっつごー」
※※
なんの根拠もなく私達は目についた路地を、手当たり次第歩いていく。
表通りよりもいっそうさびれた細い路地は、旧い家屋に挟まれて、洗濯物が揺れていたりかすかなテレビの音が聞こえてきたりする。
それは私が住んでいた町の景色とも全然違うんだけど。
どうしてかな。妙に懐かしくて……子どもの頃から知っていた道を行くように、私は歩いていく。
と、その時……
「ねぇねぇ、羽依里。なんかお店があるよ」
「店?」
民家の並んだ途中に、異質な風情を漂わせる一軒家がある。
玄関にはぼろぼろの看板がさがっていて、漢字で一文字『鞄』と彫られていた。
「鞄屋さんだって!」
「ええ。こんなところに……鞄屋? 『鞄さん』のお家じゃないよな」
「この際それでもいいから、いってみようよ」
「いい加減な」
お店?らしき建物をのぞき込む。
だいぶ年季のはいったガラスのディスプレイには、革の鞄が飾られている。確かに、鞄屋さんらしい。
そっと玄関の扉に手をかけると、ゆっくりと開いていく。
磨りガラスからさしこむ光だけに照らされた、薄暗い店内に私と羽依里はそっと入っていく。
……店内は薄暗く、ところせましと革製の鞄が並んでいる。
「あれ、いらっしゃい」
カウンターの奧から白髪に丸眼鏡をかけたおじーさんが顔を出す。
若いお客さんが来るのが珍しいのか、眼鏡を直しながらしげしげと私たちを見つめた。
「あの、これなんですけど。キャスターのところが壊れちゃって見てもらうことはできますか」
「ふむ? これまたずいぶんと古いスーツケースじゃな。ちょっといいかな」
おじーさんはよいしょと、手慣れた動きでスーツケースを台の上にのせる。
「ふむ……ふむ……ふむぅ??」
スーツケースを調べながら、おじーさんがうめいている。
「ふむぅ? おう……おう」
不思議な相槌をうつおじーさん。
「ど、どうしたんですか」
「なんと、これは……うちで作った鞄じゃないか」
「え、ええええ」
私と羽依里は同時に、声をあげた。
「これ、パパのスーツケースなんです。じゃぁ、もしかしてパパはここで……」
「あぁ……そうじゃ。覚えておるぞ。こんな店でスーツケースを買っていく客なんてまずいないからの。これも、ただの展示用のつもりじゃったんだが。あの日は……」
おじーさんは懐かしそうに目を細めながら宙を見つめる。
「若い夫婦がやってきての。確かお土産を買いすぎて、急遽スーツケースが必要になったとか」
「若い夫婦……パパとママがここにきて、これを買った……?」
「うん。間違い無い」
「あのこれ、修理って可能ですか」
「ふーむ。なにせ昔のものだからの。まったく同じ部品はないが、それでも替わりになりそうな部品ならある。少しそこで待っておってくれ」
おじーさんは店の奥にある棚をごそごそと探し始める。
「しかし君が、あの時の子ということか。こいつはすごい」
部品を探しながら、おじーさんが話す。
「ええ!? 私はその頃まだいなかったはずですが」
「いやいたよ。……ちゃんと、お腹の中に」
「あ……」
「仕事が忙しかったけど……奥さんが妊娠して休みに入ったとかで、遅めの新婚旅行と言っていたよ。仲の良い2人だった」
「そうなんだ……」
「すごい偶然だな」
「うん」
パパとママが新婚旅行でこの島に来ていた。
そしてその時、私もすでに……ちゃんと存在していたんだ。
「それで、君達も新婚旅行でこの島に?」
「は!? ちちち、違います! お宝を探してるんです」
「おたからをさがしてる??? ほっほう。それは、子宝のことかの」
「ぶ──」
私ははげしくむせた。
このおじーさん、ちょっとセクハラ気味……
「違います。海賊船を探しているんです」
「か、海賊船とな。……ふむ、昔は少し行ったところに模型屋があってな。ワシの幼馴染みがやっていたが」
「そうじゃなくて本物のかいぞく……むごごご」
食い下がる私の口を、羽依里が後ろからおさえた。
「いやいや、観光ですよ」
「ふぉっふぉ。そういえば君のご両親も、何かを探してこの島に来たと言っていたな」
「なんと。パパ達も海賊船を?」
「いや、なんだったかな……何か言っていた気がするんだが。……っと、あった。これじゃ」
おじーさんは棚の中からキャスターを取りだし、鞄にもっていく。
「うむ、これならはまりそうじゃ。取り付けるのに少し時間がかかるが、どうするかね」
「うーん。じゃぁ、そのへんぶらぶらしてようか」
お店の中はだいぶ狭くて、ここで待たせてもらうのも迷惑になりそうだった。
それになんだか私も、落ち着かない気持ちだった。
パパ達もここにきて、何か捜し物をしていた。それってなんだろう?

※※
「どこに行く?」
とりあえず店から出た私と羽依里は、細い路地を眺める。
「海の音が聞こえるね」
「そうだな。歩いているうちに、けっこう海の方まできていたんだな」
「向こうかな」
細い路地の向こうに、かすかなきらめきが見える。
海に反射している光かもしれない。
と……
「蝶々」
綺麗な、細い路地をゆらゆらと飛んでいる。
「蝶? どこに?」
「ほら、あれ」
「んん?」
「行ってみよう」
「お、おい!」
飛んでいく蝶を私は小走りに追っていく。
『見て。向こうに海が見えるわ』
『うん。あそこだ』
歩きながら、誰かの声が聞こえた。
私はその声を知っている。
泣きたくなるぐらい、懐かしい声。
※※
「おい、鴎。どこまで……」
「ここは……」
路地を抜けて小さな階段をのぼる。
そして、そこは……海を目の前に眺める、岸辺になっていた。
日差しをあびて、海はキラキラ輝いている。
そんな輝きの中へと、蝶は消えていった。
岸辺の両端は切り立った崖になっていて、小さな柵がつけられている。
街を背中にして、まわりを海に囲まれた小さな空間。
なんだか世界から隔絶された場所みたいだった。
「ふぅ」
少し脚が痛む。蝶を追いかけて、無意識に走ってしまった。
「なんか疲れちゃった。横になろう」
「調子のって、歩きすぎだ」
「ほら、羽依里も。気持ち良いよ、ここ。木陰になってるし」
「まったく」
私と羽依里は木陰に座り込む。
そのままぼんやり海の音を聞きながら空を見ていた。
一日いろいろなところに行った疲れもあり、しだいに私の意識は眠りに誘われていく。
半分落ちかけたまぶたの向こう。ふわりと、ひとひらの蝶が飛んでくる。
私はそっと手をのばす。
蝶がふわりと、私の指先にとまるのを見た。
『いや、悪いね。今日は体調悪くて』
『まったく。女の私があなたをスーツケースに乗せて推していくなんて、ひどすぎだわ』
『だいぶ改良してあるから、君の力でも苦ではないはずだよ』
『そういう問題じゃ無くて。……まぁいいわ。で私達はどこに向かってるの? こんな路地を通って』
『ほらあそこだ。もう少しがんばって』
『はいはい……。ここ……? きれいね。海に囲まれた崖……』
『うん。この景色を見せたかったんだ。5年前にフィールドワークにきて……この夕焼けを見て。絶対に君と見ようって決めていた』
『ありがとう』
『ねぇ。次は……3人で見られたらいいわね』
『うん。そうだね』
「おい。おーい」
「え」
呼びかける声に、私はうっすらと目をあける。
羽依里があきれ顔で私をのぞき込んでいた。
「いつまで寝てるつもりだ。夜になるぞ」
「え、ええ」
見ればあたりは、薄暗くなりはじめている。日暮れ間近だった。
「そんなに寝ていたんだ」
水平線の彼方には、太陽がゆっくりと沈みながら空と海を赤く照らしていた。
「きれいだね」
「まぁな」
ぼんやりと、私はさっきまで見ていた夢を思い出していた。
あれは夢? あるいは私の記憶……。
そうか。パパとママも、そして産まれる前の私も、この島に来ていたんだ。
その時のこと、もしかしたら覚えていたのかな。
路地裏を探索してるときの、懐かしい気持ち。
偶然見つけた鞄屋さん。
そして、二人が夕日を見た岸辺。
そこにたどりつけたのは、私がお腹の中からその光景を感じていて、かすかに覚えていたからかもしれない。
だとしたら、すごいことだよね。
※※
「ほら、直ったよ」
鞄屋さんに戻ってくると、おじーさんはとっくに修理を終えてくれていた。
新しいキャスターをとりつけたスーツケースを渡してくれる。
「ありがとうございます! あの、お値段のほうは……」
「いいよ。永年保証がうちの売りでね」
「ほんとですか。ありがとうございます」
「いやいや、親子二代にわたって使ってくれるなんて、こちらこそうれしいよ」
「えへへ」
「そうそう、思い出した。お前さんのご両親のことだ」
「え?」
「この島をめぐりながら、名前を考えていると言っておった」
「名前って」
「私の?」
「うん。この島が好きだから、この島で大事な子供の名前を見つけたいんですって。そうだ、そんなことを言っていたな」
「それで帰りがけに寄ってくれて、名前決まったとか言っていたな」
「決まったって……つまり、私の名前が決まったってことだよね……」
「鳥が飛んでいるのを見たそうだよ」
「その光景がすごくきれいで、その時に名前はもう決まったって」
「そうか、それで私は……」
「君は……うみねこちゃんなんだね」
「はい。久島海猫です。こんにちは」
と自己紹介をしてから、私は慌てて打ち消す。
「いやいや、鴎です。うみねこ違います」
「あれ、そうなのか。しかしここの海に、鴎は飛んでいないはずだが」
「もしかしてご両親、うみねこと鴎を勘違いしたんじゃ」
羽依里が推理を口にする。
「そんなバカな理由嫌すぎる……」
──うみねこ?──
懐かしい声が聞こえた。
「あ……」
「鴎?」
ふっと、私はさっき岸辺で寝転びながら見ていた夢の続きを思い出していた。
『名前、決めたわ。うみねこよ』
『な、なんだって?』
『あそこで飛んでいるうみねこみたいに、元気な子に育ってほしいわ』
『作家のセンスにはちょっとついていけないな』
『ダメなの』
『うみねこちゃんって、のは……うーん』
『可愛いわ』
『せめて、鴎ちゃんとか』
『あれは鴎じゃないわよ』
『そうだけど、似たようなものさ』
『似たようなものって。あなたも、学者のくせにいい加減ね』
『それとこれとは別だからね』
『鴎……久島鴎……。でも良い名前かもしれないわね』
『だろう』
「鴎?」
「へ?」
ぼーっと物思いにひたっていたらしい。羽依里の声で我に返る。
「大丈夫か?」
「う、うん。ごめん。あの、おじーさん、ありがとうございます」
「あぁ。今度は君たちの子供がそのスーツケースを持って現れるのを楽しみにしてるよ」
「い、いやいやいや。だから。そもそもおじーさん、いくつまで生きるつもりですか」
「はっは」
※※
鞄屋さんを後にして、私達は帰路につく。
日はほとんど落ちかけて、空にはうっすらと星が浮かび上がっていた。
新しいスーツケースにまたがって、羽依里に押して貰いながら、
私は空を見上げていた。
「ね! 羽依里。私達も見つけられるかな」
「え、え」
私の言葉に、羽依里は妙に動揺している。
「見つけるって……その……子供の名前?」
「ぶっ」
危うくスーツケースから落ちかけた。
「な・ん・で・よ」
「いや、話の流れから」
「海賊船だよっ」
「あ、あー。そっちね。てかほんとにあるのか」
「当たり前だよ。あるに決まってるの」
「どこからそんな自信がくるのか」
羽依里が呆れている。
どこからって。それは、この路がいつか来た道だから。
子供の頃に皆で通った道だって知ってるから。
ひげねこ団の皆と大冒険を繰り広げた道。
大事な思い出に続く道。
「じゃぁ、スーツケースも新しくなったし。明日から改めて、海賊船を探してしゅっぱーつ!」
「はいはい」
スーツケースは軽快な音をたてて、いつか来た道を再び進み始める。

©VisualArt's / Key