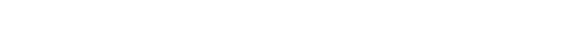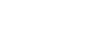「Summer Pockets」 ショートストーリー ~夏の眩しさの中で~【岬 鏡子 編】
<瞳>
母屋の離れにある土蔵の中には、所狭しと様々な珍品が保管されていた。
最初おばーちゃんにこの蔵を見せて貰った時にはちょっと面食らったけど、すぐにここが私のお気に入りの場所になった。
私はそんな蔵を全部整理し直すために大量の骨董品の出所を可能な限り調べ、目録に書き込んでいく。誰かにゆかりのある物なら、その方に連絡をする。引き取り手のないものは、まずは親戚に引き取り希望者がいないかうかがいをたてる。いないなら役所に連絡して、必要としている人がいないか調べて……それでも引き取り手がなければ、とりあえずは蔵に置いたままとなる。
たまに本土の図書館に渡って調べ物をして。そんなことをしているうちに、一日はあっという間に過ぎていく。
もともと私は授業でもよく寝ているダメな生徒だった。それがこんな静かな蔵で1人黙々と仕事をしていたら、当然のように午睡をたらふくむさぼってしまうことになる。
昼ご飯を食べてちょっと昼寝をして……起きたら日が暮れていたなんてこともしばしばだ。昼寝をしたぶんは夜に働くことにしているので、結局、朝も夜もずっと蔵にこもりきったような生活になってしまった。ほとんど日の差し込まない蔵には、もともと昼も夜も区別がないんだけど。
そして今日も……私は目録を書き込みつつ、机にひじをつきながら、うつらうつらとしていた。
ふわりと、何かが私の頭を撫でた。
見れば、不思議な蝶がひらひらと私の頭の上を舞っていた。ぼんやりとそんな蝶を眺めながら、私はなぜか妙に懐かしくて、泣きそうになった。遠くから誰かの声を聞いた。
──鏡子──
「こーら。さぼってないで、起きなさい」
声が聞こえる。さわさわと……誰かが……私の頭を撫でている。
誰だろう?
私はぼんやりと目を開く。
「……え。あぁ、瞳じゃない」
「鏡子ぉ。まーた、居眠りしてるわね」
くりくりとした大きな眼。陽気な声。親友の瞳だった。
「あれ……私、寝てたかな」
「がっつり寝てたわよ」
「最近、寝てるのか起きてるのか分からなくなってきて。自分が蝶なのか人なのか」
「なにそれ」
「知らない? そういう故事」
「知らないし文学少女のうんちくなんて聞きたくない」
「もう。瞳は、口が悪いなぁ」
「私は本でも読んでるほうがいいから」
「えー。海行こうよ海」
「いい若い者が日がな一日、こんなかび臭いところで本ばっかり読んで。行き遅れないか、心配だなぁ」
「ふふ。瞳はなんだか親戚のおばさんみたいだね」
「ぐ。おばさんって……。確かに、時々おばさんくさいって言われるけど」
彼女は朝を告げる太陽とか、鶏とか。そんなイメージだった。まぶしくて、騒々しい。
私はそんな彼女が大好きだった。
──鳴瀬瞳。
明るくて行動的で。引っ込み思案な私とは正反対だった。けど私達は不思議とウマがあった。
彼女は少し、不思議なところがあった。
彼女は、私達には見えていないものを見ていた。嘘かほんとか、彼女には未来が見えるのだという。
でも彼女は、自分の未来は見えていたのかな。
彼女の旦那さんが亡くなったときのことを、思い出す。
「……瞳。なんていうか……大丈夫……?」
「こらこら。なによ、なんだそのとぼけた励ましは」
「ご、ごめん」
「大丈夫もなにも大丈夫でいるしかないでしょ。要するにだいじょうぶい」
いつもの笑顔でブイサインを作った瞳は、空を仰いで深いため息をついた。
「なんだか実感がわかないっていうか。死ぬってなんだろうとか、分からなくなって。それってつまり、ずっとずっと遠くに行くってことなのかなって。だったらいつか会えるかなって。そんなこと考えてる自分がいる。これって後ろ向きなのかな。前向きなのかな」
「分からないけど。でも、そんなに悪い顔してないよ」
「うん……。ねぇ、鏡子。お願いがあるの」
いつになく彼女は真剣な顔だった。
「いつかあなたの前に、女の子が現れる」
それは、瞳の得意の予知だった。彼女はそれを時におふざけで、時に本気で、私に伝えてくれた。
それが他愛のないことでも、ちょっと深刻なことでも、彼女はしっかりと的中させてきた。
だから不意に彼女が私に予知を伝えてきたことに、少なからず緊張した。
「いつか? 女の子? 漠然としてるね」
「でも会えば分かるから。この子のことだって」
「うんわかった。女の子が現れる。会えば、分かるんだね」
「それであなたに、その子を助けてほしいの」
「うん。助けるよ。でも何をすればいいの?」
「ただ、見守ってあげてほしい」
「見守るの?」
「うん。あんたが私にそうしてくれたように。見守ってあげて」
「え?」
「ありがとう。鏡子。あいつがいなくなった後も、そっとそばで見守ってくれて。それに……これからしろはを置いて島を出ようとしてる私を、あんたはやっぱり見守ってくれている。私にとってそれがどれだけ、力になっていたか、きっと鏡子は知らないんだね」
「……瞳。分かった。で、それだけでいいの? その子を見守っていればいいの?」
「ううん、もう一つある。あなたは、きっと男の子にも会うことになるわ。その子の手伝いを、あなたは必要としている」
「うん……男の子にも会うんだねもしかしたら、私がその子の手伝いを必要としてる? 私にも大変なことが起こるの?」
「ううん。ただ、人手が必要なだけ。でも、あなたを手伝えるのはその男の子だけなの。それで本当にその子が手伝うに相応しいかは、あなたがちゃんと見極めるの。あなたの仕事を手伝う資格があるか……それを見て」
「うーーーーん。だんだん、抽象的になってきたわね」
「ごめんね。私に言えるのは、これだけだから」
「もう予知というか、預言者みたい。私は勇者かなにかなの。汝やがて剣をもって魔王を討つため旅にでるだろうって」
「あはは。ほんとだ。でも、きっとあんたにしかできない大事なことだから……お願い、鏡子」
「瞳、あなたは……一体……私に何を託して、どこに行こうとしてるの?」
──お願い、鏡子──

「あれ……」
ぼんやりと、机から身体を起こす。
蔵の中で作業をしながら、眠っていたらしい。
時計を見ると16時をまわっていた。
「ん……」
夢を、見ていた。いつの夢か分からない。
詳しい内容は起きた瞬間に消え去ってしまった。ただ学生時代の親友と話していたことだけは覚えてる。でもいつのことだったか思い出せない。
「あれ?」
母屋の方から何か聞こえる。チャイムが鳴っているんだ。
こんな時間に来客なんて、珍しいな。慌てて私は玄関へ向かう。
「はーい。今開けます。どうも……って……」
「どうも!」
ドアを開けると、女の子が立っていた。
「えと、あの……どちら様?」
知らない顔だった。近所の子?
「加藤うみです!」
「加藤……うみ……加藤って……」
「遺品整理の手伝いをしませんかっていう、お手紙をいただきました。それで、お邪魔しにきました」
「そう、なんだ」
確かに、親戚には一通り手紙を出した。蔵の中にはあるいは、親族の持ち物もあるかもしれないから。
ただどこからも連絡がないから、誰も来ないと思っていた。
「あの……」
うみちゃんは、少し不安そうに私をうかがっていた。
まぁいいか。きっと夏休みで暇してるんだろう。
「とにかく入って。疲れたでしょう」
「はい!」
……家にあがると、うみちゃんは物珍しそうに部屋の中を眺めていた。都会から来た子には古い家の雰囲気は面白いんだろう。
「ゆっくり休んでいて」と言って、私は買い物に出た。
私は1人で暮らしていたから、子供に食べて貰うようなものが何もなかった。
「でも、手伝いって言ってもなぁ」
島に1つだけあるスーパーに向かいながらつぶやいた。あんな歳の子に任せられる仕事じゃないよね。さすがに。
それに寄越すなら寄越すで、あの子の親から連絡ぐらいあるはずなのに。
お店に向かいながら、私は考えていた。確認の電話ぐらい、こちらからしたほうがいいのかな。
「うーん……まぁいっか」
深く考えないのは、瞳に言わせれば私の長所の1つらしい。
「ただいまー」
家に戻ると、ぱたぱたとうみちゃんが走ってきた。なぜか、身体には自前?のエプロンをつけていた。
「おかえりなさい! あの、お風呂掃除しておきました」
「え、いいのに。そんなことしなくても」
「いえ、お世話になる以上はこれくらいさせていただきます」
しゃきっとした敬語で答えるうみちゃんに、私は感心せずにはいられない。家では、さぞしっかりとしていたんだろう。
この年齢で、いじらしいというか。どういう暮らしをしているのかなって、少し心配にもなる。
──翌朝。
「それで、私は何をお手伝いしたらいいですか。蔵の整理をするんですよね」
「え……そうだね」
朝ご飯(うみちゃんが作ってくれた)を食べた後、うみちゃんは働く気まんまんで腕まくりをしていた。
「今はいいよ。ほら、せっかくだし遊んできたら」
「遊ぶって……なにをしましょう」
「なんでもしたらいいじゃない。この島にはなんでもあるよ」
「そう、ですか?」
案内がてら、うみちゃんと2人で外に出た。
日中の日差しは私に少し強すぎて、普段はあまり外を出歩きたくない。
けど今日は調子がよくて、私はずいぶん寄り道をしながら歩いていた。
「うみちゃん?」
うみちゃんは立ち止まり。海をじっと眺めている。
「ここでおとーさんは……」
「おとーさん?」
「え、ううん! なんでもないです」
何もわからないけど、うみちゃんがここに来た理由はそんなに単純じゃない気がした。
この歳で一人でやってくるには、それだけの理由があるんだ。
でも、あまり詮索することでもないよね。
「そうだ。そのうち、もう1人男の子が来る予定なの」
「え??」
「会ったことはないと思うけど、親戚の子だよ。うみちゃんよりはちょっと歳上かな。鷹原羽依里君っていうの。きっと一緒に遊べるよ」
「嫌です」
即答だった。
「そ、そう」
女の子っていろいろあるよね。
「嫌ですから」
うみちゃんとの2人の生活が始まった。
最初は戸惑っていたものの、うみちゃんは毎日外に出てはいろんな遊びに夢中になっているみたいだった。
港で釣りを教えてもらい、どこかの家のお年寄りのお手伝いをしてお菓子をもらって。毎朝、ラジオ体操に参加して……。夏休みを満喫する、ごく普通の小学生の女の子になっていた。

私にも……あの子ぐらいの子供がいてもおかしくなかった。
瞳にはそれこそ、もっと大きな子がいる。
私は昔からのんびり屋だった。マイペースにやっているうちに、いろんなものに取り残された。多分、いくつも大事なものを取りこぼしてしまった。それが大事だって気づく前に。
都会ではもっともっといろんなもののスピードが速くてせわしなくて。とてもついていけなくて。
たくさんのものを取りこぼしているようで。その感覚さえ分からなくなっていって。
そうして私はこの島に帰ってきた。この島は私みたいだ。
……蔵で作業をしていると、ここが現実なのか夢なのか。時々分からなくなるときがある。
本当は、この世界にそんな区別なんて存在しないのかもしれない。現実とか夢とか。今とか昔とか。
蝶は、あっちにひらひらこっちにひらひらと飛んでいる。蝶はそうやって今も過去も行き来が出来るのかもしれない。
私は、島に戻ってきた日の自分を思い出していた。
加藤から岬に苗字が変わった私について、あれこれと噂は飛び交った。
でもそれは、もともと養母であるおばーちゃんと、私の本当の母との間の約束でもあった。
私が成人したとき、私がどちらかの苗字を選ぶっていう。
そうして悩んだ末に、私は岬を選んだ。どうしてかな。ほとんど会ったこともない実母への思い?
……私は多分、加藤鏡子という名前を都会に置いてきたかったんだ。
「今日からお世話になります。岬鏡子です」
「うんうん。好きなだけいたらいい。この広い家に年寄り1人じゃもったいないからね」
「ありがとう。おばーちゃん」
前触れもなく帰ってきた私を、おばーちゃんは特に理由も聞かずに暖かく受け入れてくれた。
「まぁ、あっという間に、この広い家に鏡子1人になるかもしれんがね」
「まだまだ元気そうだよ」
「はっは! ろうそくの火は消える直前が一番燃えるというからの」
「またそんなことを」
「あのな。私がいなくなっても……あんたがそうしたら、ここで過ごしたら良い」
「うん……。ありがとう」
「ただ、私が死んだらあの蔵を……整理してほしいんや」
「蔵って、あの? あそこにあるのは、なんなの」
「さぁ、じーさんが集めたものもあるけど。ほとんどは、いつの間にかあそこに集まっていたんよ。誰かの遺品であったり、寄贈されたものであったり。そういう行き場のなくなったもろもろが適当に置かれているんよ。……それはそれで良いと思ってた。けど、ずっとあのままにしておくものじゃないきがしての」
「帰るべき場所に、帰らないといけない時は、来る。だから、その手伝いをしてやってほしいんよ」
「うん。分かった」
短い間だったけどおばーちゃんと2人で過ごした時間は、楽しかった。
ある寒い日に、おばーちゃんは眠ったまま起きてこなかった。とても静かに逝ってしまった。
私は1人になった。
そしてこの蔵でおばーちゃんの言葉通り、整理をしている。
「ふぁ……」
今日も眠い。私は書きかけの目録の上につっぷして、静かに目をつぶる。
重たいまぶたの向こうで、何かが窓から入ってくるのが見えた。
「蝶……?」
不思議な色の蝶だった。
蝶は何かをさがすように蔵の中を漂い、やがて私の頭の上を飛び始めた……。
──鏡子、起きなよ──
ぽんぽんと、誰かに頭を叩かれて私は目を覚ます。
「あぁ、瞳……来てたの?」
瞳が私を見下ろしていた。
あれ?瞳がいるということは……私はまだ、昔の夢を見ているのかな。
でも、棚には整理している最中の骨董品が並んでいる。
じゃぁ、これは今なのかな。
夢に今も昔も関係ない、か。
「ねぇ、瞳」
私は顔だけ少しあげて、ぼんやりと声をかける。夢の中の瞳に。
「女の子、あなたが言った通り、来たよ」
「うん。どうだった」
「楽しそうにしてたよ」
「毎日外で遊び回って、帰ってきたら疲れ果ててぐっすり眠って。朝はラジオ体操に行って」
「そっか。良かった」
見たこともないような、瞳の優しい、うれしそうな顔だった。
しろはちゃんに向けるより、もっと、大人びたような。穏やかな顔だった。
こういう顔を私は最近、どこかでよく見ていたような気がする。
そうだ……おばーちゃんが私に向けていた笑顔。
「でも悩んでるみたいだったよ。この島に、大事な用事があるみたい」
「うん」
「瞳はあの子を知ってるの?」
「……うん。少しね」
「うみちゃんは……大丈夫なのかな。歳の割にはすごくしっかりしてて、逆に心配なの」
「もうきっと大丈夫だよ。鏡子のおかげ」
「そっか……」
それなら良かった。本当に良かった。
「ねぇ。鏡子は? 夏が楽しい?」
瞳が優しい声で聞いてくる。
「私は? 私は…………分からないよ」
「……そっか。それもしょうがない、か」
瞳は背中を向けて出口へ歩き出す。
「瞳は行ってしまうの? もう、帰ってこないの」
「分からない。でもそうだね。おそらく、ここには、帰ってこられない。そのかわり、目的も行き先ははっきりとしているから。もうすぐ、私の旅も終わると思う」
「……そっか。じゃぁね、瞳」
──じゃぁね、鏡子──
「鏡子さん」
「はい!」
え、あれ?目の前には、心配そうに私をのぞき込む男の子。
「あれ。羽依里君、いつ来たの」
「いつ来たって……一週間前から来てたじゃないですか」
「????」
私はしばしぼんやりと考える。
たしか女の子が訪ねてきて……。私はその子と過ごしていたような。
ううん違う。甥の羽依里君が来たんだ。おねーさんからもちゃんと連絡があって。
あれ、でもやっぱり女の子も来てたような。それで私達は3人で……。でも、女の子って誰のこと?
「羽依里君は、1人でこの島に来たんだよね」
「え、は、はい。そうですよ」
「えと、あれ? 妹さんと一緒じゃなかったっけ」
「しっかりしてください。俺、妹なんていないですから」
「あれれ。おかしいな……」
寝起きの頭は、夢と現実がごちゃごちゃになっているのか、少し混乱していた。
「カップうどん食べかけで寝ちゃって……鏡子さん、大丈夫ですか?」
「え? 食べかけ? カップうどん?」
「それ、のびてますよ」
「ああああああ」
机に置かれたカップ麺は、だいぶ時間がたった後らしく、冷めて麺はぐったりとしていた。
「食べながら眠る人なんてはじめて見ました」
「……あはは」
「またカップうどんですか」
「食べる?」
「いやです! そもそものびてるじゃないですか。そんなものばかり食べてると、筋肉つきませんよ」
「や、私は身体を作りたいわけじゃないから」
「でも健康によくないですから」
「そう言えば、羽依里君はどうしてここに?」
「蔵の整理、ちょっと休憩です」
「蔵の整理? どうして?」
「え? だってそのために来たんですし」
「そ、そうだね」
……ん?デジャブ。似たようなやりとりをしたような気がする。どこかで。
今みたいに羽依里君から手伝わせてくださいって言われて、そのとき、私は断った気がする。
まだ、その時じゃないと思ったから。
でもいつのことだろう。今年以外にも、羽依里君はここにきたことがあったかな。
私は少し考える。
蔵の整理、か。目録を作るのは私として、他の作業はお願いしてもいいかもしれない。
正直なところ、棚の整理はまったく進んでいなかった。本当は、雑然としたこの場所が、私は好きだった。ずっとこのままにしておきたかった。
でも、おばーちゃんに頼まれたんだから、本当はそれじゃだめなんだ。
この夏の間に、ちゃんと整理を終えないと。
でも、なんとなく分かっていた。私には、無理なんだ。
──その子の手伝いを必要とするわ──
羽依里君がそれをしてくれるような気がした。だから……
「じゃぁ、羽依里君、続きお願いするね」
「はい! 任せてください」
……いったん始めると、羽依里君は夢中になって作業を続けてくれた。
かわりに蔵に閉じこもっていた私に、手持ち無沙汰な時間が出来た。
私は料理なんてしてみた。いつ以来だろう。もともと、苦手じゃなかったんだ。だけど、全然やらなくなっていた。
せっかく作ったけど、羽依里君は熱中しているのかほとんど蔵から出てこない。
私はゆっくり味わってご飯を食べてお風呂に入って。自室で寝ることにした。
それは久しぶりの、深い深い、夢さえ見ない眠りだった。
……目が覚める。いつの間にか、朝が来ていた。
「おはよ~」
居間へ行くと、羽依里君が朝ご飯を食べていた。
「おはようございます。……あれ、鏡子さん、大丈夫ですか。少し顔色が悪いですね」
「ううん、大丈夫。いつも寝ない時間に寝たせいかな」
「いつも寝ない時間って……ちゃんと夜に寝ただけじゃないですか」
「そうだね、変だよね」
同じようで違う夏が過ぎていく。
ゆっくりと流れていく大きな雲を眺めながら考えていた。
あの蔵を立ち止まる言い訳にしていたのかも知れない。
だとしたら。
蔵の整理が終わったら……、私は歩き出すことができるんだろうか。
……どこへ?
やがて8月のカレンダーが終わろうとする頃。
「あの、終わりました。蔵の整理」
「え、ほんと?? すごいね」
あんなに散らかった蔵を、整理しちゃったんだ。というか、今まで私はなにしてたんだろう。
羽依里君は恥ずかしそうに笑う。
「終わったと言っても俺なりに、ですけど。夢中になっちゃって」
羽依里君について蔵へ行く。
そして中へ入り、私はその光景に立ち尽くしていた。
脈絡なく押し込まれていた骨董品の数々は、今は一目に整然と並べ直されているのが分かる。それだけじゃなくて……そこのは、不思議な秩序があった。蔵の中でこんがらがっていた目に見えない何かが綺麗に並び替えられていた。
それは私自身の記憶さえ整然と思い出させてくれるような気がした。
どうして私が島を出て行って、そしてどうして戻って来たか。
忘れるわけがないけど、どこかに追いやろうとしていたいろんなものが、整然と私の心の中にも、並べられていく。
狂っていた時間が、戻っていくんだ。
そこには胸を締め付ける辛い思い出があって……。大事なキラキラとした思い出もそこにはあった。
私の夏には、わりきれないもの、忘れられないもの、いろんな思い出が、混在していて、どういう風に整理したらいいのか、私には分からなかった。
だけど……これで……やっと……
──時の迷い路から抜けだせた──
そんな不思議な安堵を確かに感じていた。
はじめてこの蔵に入ったとき、おばーちゃんに聞いたことがある。
『この蔵はなんなの、おばーちゃん』
『うーむ。なんというかの。鏡子は、こないなことはなかったかの? 幼い頃、外で遊んでるときに、何か見つけたりして』
『何かって?』
『そうやの。ちょっと変わった形の石とか誰かにもらったガムとか。お菓子のおまけとか。それで、それを大事にポケットにいれたりしたことないかい?』
『うん……あると思う、そういうことも』
『うん。私でさえあったよ。子供の頃。ポケットに入れて、チャックをして……こぼれないようにして。とても大事にしまって。でも、翌日には忘れてるんや。それで、いつの間にか無くなってるの。でも、ふと思い出して……ポケットをさぐると、その欠片が残ってたりするんよ』
『欠片が……残ってる』
『うん。それは本当に小さな欠片で。それが何なのか思い出せなくて。それでな、この蔵は、そういう場所なんだよ。誰かの大事な何かをそっとしまう場所。そうして、忘れられた場所』
初めて羽依里くんがこの蔵の中を見た時「おばーさんは、一体何をしていたんでしょう」と、口にした。
だから、私はおばーちゃんと同じ話を羽依里君にしてあげた。
確かにこの蔵には、何か不思議なものが宿っている。今の私には、それがなんなのかおぼろげに分かる気がした。
おばーちゃんはそれを知っていたんだろうか。それで私に整理を任せたんだろうか?
「ねぇ羽依里君」
「なんですか」
「頭なでて」
「……は?」
「うそうそ、冗談だよ」
「は、はぁ……どうしたんですか」
「なんでもないの。むしろ逆だよね。頭なでてあげようか」
「い、いいですよ。どうしたんですか。鏡子さん」
「なんでないの。ごめんね。蔵の整理ありがと……」
と、不意に私の頭に羽依里君の手がのせられた。
「お、おお?」
遠慮がちに、羽依里君の手が私の頭をなでていた。
私は驚きつつも、そのままそこにいた。なんか妙に気持ち良い。猫になった気分。
「……疲れてるんですか、鏡子さん」
「あはは……」
自分でお願いしておいて、私は照れてしまった。
羽依里君も恥ずかしいのか、すぐに手を引っ込めた。
「お、お疲れ様。助かったよ。埃だらけだったしお風呂、入ってきなよ」
「はい、そうさせてもらいます」
羽依里君は蔵を出て行った。
その後も、私はしばらく1人で佇んでいた。
整理された光景の中で、私は思い出していた。
あの頃の、夏を。そこにいた自分の姿を。
──加藤鏡子。
都会に出て夢を追いかけて、そうして挫けて帰ってきた若かった自分。
夢のように忘れていたあの頃の自分を私は今、とても久しぶりに思い出していた。
……ひぐらしが鳴いていた。
あんなに強かった日差しが少し柔らかくなっているのに気がついた。
「そっか……」
──その子を見守って上げて──
──それはとても大事なことだから──

「もう……私の役目は終わったんだ。そうなんだね、瞳」
隙間からこぼれてくる西日を浴びながら。
そこには、あの頃とかわらない笑顔を浮かべた親友が立っている。
「役目が終わったんじゃない」
言いながら瞳はそばに来ると、私の頭を優しく撫でてくれた。
「夏休みが終わったんだよ。鏡子」
©VisualArt's / Key