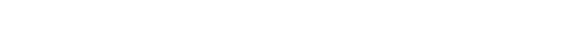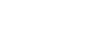「Summer Pockets」 ショートストーリー ~夏の眩しさの中で~【水織 静久 編】
<胸に抱いた柔らかなもの>
それは夏のある日。
私は紬と羽依里くんを待って、灯台にいた。
「二人とも、駄菓子屋でお買い物かしら?」
この灯台が、こんなに静かなのは珍しい。
まあ、廃灯台なんだから、本来は静かなものかもしれないけど。
でも、その灯台を見ていると……紬と出会ったあの日のことを思い出す
そして、口から自然と、思い出の言葉が漏れた。
「……おっぱい」
その言葉は、小さな波の音へと消えていく……。
そんな静かな時間を楽しんでいると、二つの声が聞こえてきた。
片方は、少し意外な声。
「おい鷹原、嘘をつくな」
「ホントだ。静久と仲良くなるなら、おっぱいの話をするのが一番なんだ」
「信じられん……」
「騙されたと思って」
「騙されてた場合の被害が大きすぎるだろ!」
その声の主は、羽依里くんと加納くんだった。
羽依里くんはともかく、加納くんがここにくるのは珍しい。
「よう、静久」
「おはよう、パイリくん。加納くんもいらっしゃい」
「は、はい! いらっしゃいました!」
加納くんはよく、私の前だと緊張したように姿勢を正したり、緊張したような振る舞いになる。
私が生徒会長だから気を使ってるのかもしれない。
「ほら、天善。おっぱいの話をしろ」
「こ、このタイミングでか!?」
「静久には挨拶レベルでおっぱいの話をした方がいい」
「う……む……。信じて……いいんだな」
「どうしたの、二人とも?」
「ああ、天善が静久に話があるらしくて」
「あらそうなの? どんなお話かしら?」
私が加納くんに視線を向けると、彼は目をそらせながらこんなことを言い出した。
「に、肉体というのは……日々の修練と、意識の結果だと思います……。自堕落さも、努力も、すべて肉体に現れると……自分は思います」
「そうね。私もそう思うわ」
「な、なので……その……水織先輩の母性は、優しさは、素晴らしいと思います! それがその素晴らしい胸に現れているのではないでしょうか!?」
「え? あ……ありが……とう」
急におっぱいを誉められて、心臓が少しだけ……トクンと音を立てた。
「その! 胸を誉めたのは、性的な意味ではなく、人間の肉体の美しさと言いますか……美術品のような意味でして!」
「私のおっぱいが……美術品!? ちょ、ちょっと待って加納くん……そんなに急に褒められたら、どうしていいのかわからないわ……」
耳が……熱くなってきた。
「た、鷹原! こ、これは照れてらっしゃるのか!?」
「これだけ顔も赤いんだし、きっとそうだろ」
「――っ! 感謝する! よし、このまま俺は! 一世一代の発言をするぞ!!」
加納くんは、少し照れた表情をしたまま、まっすぐ私に向き直った。
そして覚悟を決めたように口が開いていく。
「み、水織先輩!」
「は、はいっ!」
「……あ、あなたの胸は……まるで白いピンポン玉のようだ」
「あ……」
「俺に……サーブ権をください!」
そう言って、私の目をじっと見つめた。
私は……それに対して……。
「……グランドピンポン」
「え? ……は?」
「加納くん……加納くんは卓球が『テーブルテニス』という呼ばれていることについてどう思う? まるでテニスの劣化したもののような名前だと思わない?」
「た、確かに!」
「そんな名前を付けられて、悔しくない? むしろ、テニスの方が卓球の亜種。グランドピンポンだと思わない?」
「――っ!!」
「それと同じ。あなたはおっぱいを白いピンポン玉って言ったけど、おっぱいはね……おっぱいなの。おっぱい以外で語っちゃダメ」

「おれ……は……なんてことを……」
加納くんが膝から崩れ落ちてしまった。
「……間違いは誰にでもあるわ。大丈夫、おっぱいは……間違いすら包み込むような柔らかさを持っているの」
「なんと……慈悲深い! 確かに……この世界はすべてを包み込む」
「いや、天善。静久が言ってるのは世界じゃなくておっぱいだ」
「水織先輩がそんなことを口にするわけがないだろ?」
「え……でも……さっきからずっと……」
「しかし鷹原……ありがとう。そして水織先輩……出直してきます」
「うん、またね♪」
そう言って加納くんは帰っていった。
「なあ静久、さっき『世界』じゃなくて『おっぱい』の柔らかさを語ったよな?」
「ええ、おっぱいを語ったわ」
不思議そうな顔をしながら、羽依里くんは加納くんの後姿を見送った。
そして近くのベンチに座ったので、私もそこに腰を下ろす。
「そういえば静久は、どうしてそんなにおっぱい好きになったんだ? いつごろからおっぱいなんだ?」
「ふふっ、パイリくんは、おっぱいに興味深々なのね♪ いいわ、おっぱいを教えてあげましょう」
「いやいやいや、おっぱいじゃなくて、静久のことを知りたいんだ」
「えっ? あ……そ、そんなこと言われると……照れちゃうわ」
羽依里くんも自分の発言に気が付いたようで、軽く謝りながら照れたような表情を浮かべた。
私は、少し顔を反らして灯台の方に顔を向ける。……思い出す。紬と会ったあの日のことを……。
「私がおっぱいになったのは……紬と出会った時からね」
「そうなのか」
「ええ、懐かしいわ……」
「……ん? でも……紬とあった時ってことは、おっぱい大好きになってから、まだ……」
「二ヶ月よ」
「……意外と歴史が浅い」
「おっぱいに時間は関係ないの」
「……そうなんだ」
なんとも微妙な表情をしている。
私は……そんな彼に、少しだけおっぱいの話を聞いてほしいと思った。
それこそ"このお話"の結論であるように……。
「その時のこと、ちょっと話してもいい?」
「ああ、むしろ聞いてみたい」
それじゃあ……と、私は口を開いた。
それは梅雨が明けて、終業式の数週間前のことだった。
「なるせさーん! あの……ちょっとお話させて―」
「――っ! よ、用はないからっ!」
「あ……」
白い影が、磯の岩場をひょいひょいと、跳ねるように走り去ってしまった。
結果から言うと、私は逃げられたことになる。
あまり学校にやってこない鳴瀬さん。
そんな彼女と少し話をしてみてほしいと先生から頼まれ、この鳥白島に来ていた。
彼女はただ後輩というだけで、あまり面識もなければ、話したこともなかったと思う。
ではなぜそんな私が彼女と話すことになったのか。。
それは生徒会長だから、人当たりがいいから、誰とでも仲良くできるから……ということらしい。
「そんなことないのに……」
むしろその評価は、私にとってコンプレックスだ。
変に真面目で……人の頼みごとを嫌と言えない。誰とでも話せるけど、親友のような友達がいない。
辛いって程のことでもないけど、少し寂しくはあった。
「帰ろうかな?」
時計を見ると、船の時間までまだまだある。
この島で時間をつぶせる場所……。私が知っている場所は、あそこしかなかった。
「あれ、水織先輩? どうしたんですか、こんなところで」
「こんにちは空門さん。それに、三谷くんと美希ちゃんも」
島にある駄菓子屋にやってきた。
加納くんはいないみたいだけど、たぶんどこかで、卓球の練習をしているのだと思う。
それよりも……。
「三人とも、難しい顔をしてるけど……どうしたの?」
「ああ、全然大した話じゃないんだが、この柄の名前をど忘れしてしまってな。三人で思い出そうとしているんだ」
私も、その柄がプリントされているフェイスタオルを見てみる。
「この柄だったら、ペイズリーかしら?」
「なるほど! そうそうペイズリーっスよね!」
「そうだった。確かにペイズリーだったな」
「え!? ちょ、ちょっと水織先輩……急に何言いだすんですか。良一ものみきも……よくそんなことを口にするわね」
何故か空門さんは、胸のあたりを手で隠しながら照れてしまった。
「蒼、何をそんなに悶えてるんだ?」
「だ、だって、みんなが急にパ、パイズ……とか言い出すんだもん!」
「言ってねーよ!」
「そもそも柄の話だったろ? 私たちはペイズリーって言ったんだ」
「それ、初めて聞く言葉だわ? どういうものなの?」
「い、いや。私としては、水織先輩はそういう言葉も知識も、知らなくていいと思う」
「で、ですね。なんか生々しいし」
「そうなの?」
……こういう時、何とも言えない疎外感を覚えてしまう。
真面目であるがゆえに、そういう話が出た時には気を使われて。
でも、エッチな話題も苦手だし自分から行くこともできない。
人と仲良くなるには、ある程度の『恥ずかしさの共有』みたいなものが必要だと、私は思っている。
それを自分から出せない私は、みんなとの距離を埋めていくことができない。
四人でいるけど……イメージは三人と一人だ。
「それじゃあ、私は行くわね?」
「え? 船までまだ時間ありますけど?」
「ちょっと、観光とかしていこうかなって」
「わかった。また学校で」
彼女たちと別れて、私はあまり人気のない方へと歩いて行く。
何となく一人になりたかった。
灯台にたどり着き、誰もいないそこで時間が過ぎるのを待った。
ここには私一人しかいない。
そう思っていたけれど、先客がいたようだ。
「こんにちは……。お隣、いいですか?」
そこにいたのは、クマのヌイグルミだった。
高そうな年代物……誰かの忘れ物だろうか?
何となく、それを膝にのせてギュッとしてみる。
「こういうのを触るのも、久しぶりね……」
小さな頃から、少し成長の早かった私は、ある誕生日からプレゼントが変わった。
「そろそろヌイグルミは卒業ね?」なんて親から言われて。
私はそれに「うん、もうお姉さんだもん」と答えた覚えがある。
本当はヌイグルミがよかったのに、親の喜びそうなものをねだったのだ。
その頃から、他人の言うことをよく聞くいい子を演じていたんだろう。
後輩から「胸を大きくする方法を教えてください」なんて言われたこともあった。
私はその時、その知識を勉強して、みんなに教えたりもした。
期待を裏切れない。
私は、そんな自分の性格も、発育がいい体も、エッチな話もできないノリの悪さも……好きではなかった。
ほんの少しでいいから、そんな自分を壊したかった。
だから……。
私はヌイグルミを置いて、海が見えるところに立った。
今言える、精いっぱいのエッチなことを言って……少しでも自分を壊そう。
そんな願いを込め、肺に目いっぱい空気を吸い込み、私は叫ぶ。

「おっぱーーーーーーーーーーーーーーーい!」
恥ずかしい……。
なんてエッチで、はしたないことを言ってるんだろう……私は。
でも……そんな自分を変えるために!
「おっぱい! おっぱい! おっぱーーーーーーい!」
力の限り叫んだ。
「ふぅ……」
こうしていけば、もしかしたら少しは変われるかも。
でもさすがに、こんなところを見られたら、恥ずかしくて死んでしまうかもしれない。
叫び終わり、さっきまで座っていたベンチに視線を向けると。
「……」
「……むぎゅ」
……見られていた。
「よ、よーかいですか?」
私が初めて見る金髪の女の子。
その子はちょっと怯えながら、そんなことを聞いてきた。
本来であれば『よーかい』と言われたことに、答えるべきところだけど……私は、少し違うところに意識がいっていた。
「……綺麗な髪」
「むぎゅっ!?」
お人形のような外見。
夕焼けを薄めたような、そんな印象のある髪色に、私はついそんなことを口にしてしまっていた。
「あ……急にごめんなさい。えっと……? 妖怪って、妖怪? あの、お化けみたいな」
「はい、そですね」
「私が妖怪だとして、いったい何の妖怪なの?」
「……おっぱいのよーかいです」
どうやらというか、やっぱりというか、聞かれてしまっていたみたい……おっぱいを。
今すぐ走って逃げたいけど、私はなんとか取り繕って、彼女との会話を続けた。
「私は妖怪じゃないわ。だから怖がらなくて大丈夫よ」
「そですか。えっと……おっぱいの妖怪だと思っていた方が、妖怪ではないわけですから……」
女の子は少し考えると、納得したように何度もうなずく。
「なるほど。ではあなたは、おっぱいというわけですね?」
「わ、私はおっぱいじゃないわ!?」
「むぎゅ? では、あなたは……?」
「私は水織静久よ。その制服、うちの学校の制服ね? 知ってると思うけどそこの生徒会長をしてるの」
「しりません」
「ええ? 学校にいるのに、生徒会長を知らない生徒がいるなんて……」
私はほとんどの生徒を覚えているのに。
あれ? でも……。
「あの、あなた……学校に来てる? 見たことない気がするんだけど」
「いったことないですね」
「ダメよ、ちゃんと来ないと?」
「わかりました。ではぜひ今度、連れて行ってください」
「え? 行く気あるのに今まで行ってなかったの?」
「はい。今までは、色々やることがあったんです。これからはないので、行ってみたいです!」
何だか複雑な事情がありそうだし、あまり深く聞かない方がいいのかも。
それにしても、初対面の私に「連れて行ってください」か。
人懐っこいし、反応が面白い。
「ふふっ♪」
「どうして笑ったんですか?」
「ううん、面白い子だなーって」
「むぎゅ?」
「学校は、もうすぐテスト期間になるし、それから終業式もすぐあるわ。みんなと仲良くなるなら、夏休み明けの方がいいかも」
「それはいつですか?」
「九月の一日ね」
私がそう言うと、彼女はすごく寂しそうな顔をしながら「むぎゅ~」と唸った。
その日にもしかしたら、何かあるのかもしれない。
けれど、触れられたくないことかもしれない。
だったら、あえて聞いてあげない方がいいだろう。
「あ……そろそろ船の時間だから、私は帰るわね」
「そですか……。もうちょっとお話したかったんですけど、船の時間だったらしょうがないですね」
もうちょっとお話したい? 私と?
「島には、私より面白い人たちもいるから、その人たちともお喋りしてみたら?」
「でも、あなたはいい人なので、あなたとお喋りしたいです」
「そんな、いい人なんかじゃないわよ……」
「いい人です」
「どうして?」
「ヌイグルミを、ギューッとしてたので」
「……そこから見てたのね」
「こころない人たちは、けったり投げたりします」
「そんなことはしないわよ。あら? そういえば……あのクマのヌイグルミが見当たらないけど」
「むぎゅ! ……ふ、船です! シズクさん! 船がもう来ますよ!」
「あ、そうね。それじゃあ――」
この島に来る用事なんて、たまにしかない。
それこそ今日は偶然来ただけで、さらには灯台になんて来る理由はない。
けれど私は、こう口にしていた。
「――またね」
船に乗りながら、私はさっきの発言を思い出していた。
自分でも不思議だった。
特に用事もなく、理由もなく、そんな約束をしてしまうなんて。
もしかしたら、彼女のあの人懐っこさに影響されてしまったのかもしれない。
「不思議な子ね……」
そう言いながら笑みがこぼれてしまった。
今度、島に用事がある時にでも、また彼女に会いに行ってみよう。
あの……。
……あれ?
「名前……聞いてなかったわ」
翌日、私はまた島にやってきた。
とりあえず、彼女へのお土産でも買っていこうと、駄菓子屋に行くことにした。
するとそこには、空門さんと美希ちゃんがいた。
あの子がよく買うものを聞いてみようと思うと……。
「え!? 金髪の子に会ったんですか!? あの、洋風の座敷童みたいな子」
「あ、なんかそんな雰囲気だったわ。人懐っこくて楽しい子よね?」
「なっ!? "ツムギちゃん"と喋ったのか? いや、何というか……さすが水織先輩だな」
「な、なに? "ツムギちゃん"って? この島の子じゃないの?」
「うーん。その子、都市伝説みたいな子なんですよ。時々現れて『つむぎちゃんでーす。つむぎちゃんをよろしくおねがいしまーす』って言って、どこかに帰っていくんです」
「そんなこと、全然言われなかったけど……」
「そうなのか。そういえば、梅雨が明けたあたりから、全然見かけないな」
「へー……」
その後も、三谷くんや加納くん。会った人に聞いてみると……みんな同じような回答をしていた。
でも、不思議と怖い感じや、嫌な印象は持っていないようだった。
私は、そんな聞き込みをしながら灯台に向かう。
あの時「またね」といった手前、私は彼女に会いに行くべきだろう。
……ううん、ちょっとちがう。
私もきっと、彼女ともう少し喋ってみたくなったんだろう。
だから、用事もないのにこの島に来た。
「こんにちはー」
「むぎゅ! シズクさんです」
「ふふっ、むぎゅ~♪ ツムギちゃん」
彼女の挨拶らしきそれを、私も真似てみた。
「わたしの名前、知ってるんですか?」
「ええ、駄菓子屋さんで聞いたの。漢字で書くと、糸に自由の由になるで紬……でいいのかしら?」
「糸……自由……なるほど。そですね、それがわたしの漢字です」
「ええ。じゃあそう呼ばせてもらうわ」
「今日はどうしたんですか?」
「そうね。昨日、紬ちゃんにお喋りしたいって言われたから、来ちゃったの」
「おー。やっぱりシズクさん、すごくいい人です」
「そんなことないわよ」
本当に、何となく会いたくなって来ただけなんだから。
彼女のことを思ってのことではない。
「~~~♪」
「なあに、その鼻歌?」
「楽しい時に歌うものです。私の一番のお友達が、よく歌ってました」
「そうなのね」
この子にも、いるんだ。
そういう、仲のいいお友達が。
……少し、うらやましくて……少し、悔しい。
「そのお友達は、ここには来ないの?」
「そですね……。来るはずなんですけど、ずっとここには来ていないみたいです」
「そう……なんだ」
何だか深い事情がありそうで、聞いてはいけなさそうな雰囲気だ。
なのに……何故か、私はそのことを聞きたくなってしまった。
でも……と、心の中で首を振る。
「それじゃあ、紬ちゃんの言っていた、お喋りをしましょうか?」
「はい! では、シズクさんのことが知りたいです!」
「私? 私は……そうね……」
彼女は、これといって話題があるわけでもなく、聞きたいことがあるわけでもなく……こう言うのは少しおこがましいかも知れないけど、純粋に私と話してみたかったようだ。
一つの話題が終わって、無言の時間が流れても、何となく……心地が良かった……。
なんの意味もない話をして、無駄に時間が流れて、何でもないことで笑う。
「シズクさん。昨日はどうしてで、ここに来てたんですか?」
「え? どうしてって……」
「あと、何でおっぱいって叫んでたんですか?」
少しだけ、言うのをためらった。
真面目な自分を壊したい……とか、今までの私のこととか。
そんなどうでもいいことを聞いても、彼女は楽しくないだろう。
……でも。
「なんかちょっとね、すっきりしたかったのかな?」
私はそう言った。
きっと誰かに、聞いてほしいって思っていたのだ。
どうでもいい私の思いに、踏み込んできてくれる人を……待っていたのかもしれない。
「おっぱいって言うと、すっきりしますか?」
「ふふっ……ちょっとだけ♪」
「では、わたしも……」
彼女は、昨日の私と同じように、海の方に向かって叫んだ。
「おっぱ~~~~い」
そして私の方を向きなおす。
「……実感がありません」
「そう? すっきりした顔してるわよ?」
「……言われてみれば。モヤモヤがなくなってます」
「ふふっ♪ 冗談よ」
「むぎゅ!? うそ……だったんですね。むぎぎぎぎぎ……」
「ごめんなさい♪ でも、あなた……なにかモヤモヤしてることがあるの?」
「そですね。でも、ちょっと解決しました」
「どんなモヤモヤなの?」
私は、自分の発言に驚いていた。
今までだったら『あえて聞かないであげるべきだろう』なんて思ってたのに。
彼女が踏み込んできてくれたおかげなのか、それとも……彼女に踏み込みたいと思っているのか。
どちらにせよ私は、この時点で……彼女のことを好きになっていた。
お友達になりたいって、そう思っていた。
「わたしのモヤモヤはですね。お話しできる人が少なくなってしまったので……ちょっと寂しいということです」
「そうなんだ。えっと島の人たちは?」
「むぎゅ……。変なこと言われたらいやなので……お会いしたくないです……」
「変なこと? 何か言われたの?」
「……昔、髪の色と目の色を……変な色といわれました……」
「あ……」
特徴的な金髪と、碧色の瞳。
島のお年寄り、それにまだ一人で島外に出ていない小さい子なんかにとって、少し珍しいかも知れない。
「それじゃあ……私がお友達になってあげる!」
と、そう言おう思った。
でもそれは、なんか少し違うような気がした。
きっとそう言えば、私たち二人は仲良しになれるだろう。
時々、私がここにきて、二人の時間を過ごす。
なんでもない話をして、どうでもいい時を楽しく過ごす。
きっと年齢も違うし、おそらく国も違う。
そんな二人が、誰も来ないここで仲良くしている。
うん……親友っぽい。
でも、それじゃダメな気がした。
私は彼女に、島のみんなの良さを教えてあげたかった。
「私の後輩、いい子ばっかりでしょ」って。
そして島のみんなにも、彼女の良さを教えてあげたかった。
「私の親友、かわいいでしょ」って。
だから、お節介をすることにした。
彼女に……人に、踏み込んでいくことにした。
「あのね……私、自分の胸が……あんまり好きじゃないの」
「むぎゅ? どうしてですか?」
「なんていうのかな? 大きいせいで、私も変な目で見られるからかな? 大人っぽく思われたり……頼れるって思われたり」
「わたしと、同じなんですね……」
「そうね。変な目で見られる仲間ね」
「そう言われると、ちょっとだけうれしいです」
「それに、すごく邪魔だなって思うことがあるの。こんなに大きくても、無駄で……意味がない」
でも……。
彼女と過ごした意味のない時間は……とても楽しかった。
「私はね、あなたの髪も目も、すごく綺麗だと思うの。うらやましいって思うわ」
「むぎゅっ! て、照れます……」
「私も、胸をうらやましがられることがあるわ」
「はい。わたしもかっこいいと思ってました」
「うん。きっとそういうことよ……」
「……」
彼女は何度もうなずき、そして首を傾げた。
「どういうことです?」
通じてなかった。
「周りの人からはうらやましいって思われてるの。でも、自分はそれに悩んでいる。……とらえ方次第なのに」
「つまり……どういうことです?」
「ふふっ♪ あなたが何を言おうと、私はあなたの髪が好きってこと。そしてそれをみんなに伝えたいってこと」
「おー。なるほどです」
「ねえ、触ってもいい?」
「目はいやですけど、髪ならいいですよ」
「ふふっ♪ 大丈夫、髪の毛しか触らないわ」
「だったら。……どぞです」
そう言って彼女は、私の横に座って頭を傾けてきた。
それにそっと触れて、手櫛を通すようにスーッと撫でていく。
「綺麗で、サラサラで……気持ちいい」
「あ、ありがとうございます」

くすぐったそうに、照れたように、私に笑顔を向けてくれた。
「きっと……みんなそう言ってくれると思うの? 綺麗だって」
「むぎゅ。ですが……やっぱり、ちょっと怖いです」
「みんないい人たちよ?」
「わたしはこうして時々、シズクさんが来てくれれば……それでいいです」
不安そうにそう言ってきた。
私は、彼女と……さっきまでの自分に、こう答えた。
「それはダメよ?」
「むぎゅ?」
「あのね……私これからコンプレックスだった胸に、誇りをもって生きるわ」
そう、彼女をまっすぐに見ながら言った。
「あなたが綺麗って、かっこいいって言ってくれたから、それを信じてみることにする」
「……むぎゅ」
「だからあなたも、その髪と目にコンプレックスを持たないで。……私の言うことを信じてみてくれない?」
「……」
すると彼女は……ちょっと不安そうに、ゆっくりと頷いた。
私の顔は……自然とほころんでいた。
「それじゃあ、みんなのところに行ってみましょうか?」
「わ、わかりました。……ですが、その前にお願いがあります」
「ええ、何かしら?」
「あなたがわたしの髪をキレイと触ってくれたように、わたしもそのおっぱい……触りたいと思います」
「え? さ、触るの? ……おっぱいを?」
「触ります。……撫でます」
「結構ちゃんと触るつもりなのね!」
今までの私なら、そんなの断るけど……。
「どうぞ」
私は、そう生きるって決めた。
今日から私は、おっぱいに対して肯定的に積極的に生きていく。
それを見せて、彼女を勇気づけなければならない。
「では、触らせていただきます」
彼女の手が、正面から私の胸を触ってきた。
「ど、どうかしら?」
「なんでしょう。すごく……幸せな気持になりました」
「私のおっぱい……触ると幸せになれるのね」
「なります」
「わかったわ。それじゃあみんなにも、触ってもらうわ」
「いいと思います」
「そうして私は、紬を連れて駄菓子屋に行ったの。もちろん、すぐに受け入れてくれて、今の関係になったわ」
「……」
「だから、紬の隣にいる限り……私はおっぱいでいるの。あの子が自分の容姿に、あの綺麗な髪と目に……自信を持てるように、ずっと笑顔でいるように……いつまでもおっぱいなの」
「……そうか」
「どうしたの?」
「いや……思いのほかいい話だった」
羽依里くんは、とても複雑な表情をしていた。
「あと、気になるのは……おっぱいはみんなに触らせたのか? 良一とか、天善にも……」
「その頃はおっぱい初心者だったから、結局誰にも触ってもらってないわ」
「……そうか」
「ええ、そう」
「じゃあなんていうか、ちょっと前まで結構頑張っておっぱいって言ってたんだな」
「そうね。まあすぐに、おっぱいは独り歩きを始めたたけどね」
「お、おう。よくわからない」
「でも、おっぱいのおかげで、パイリくんとも仲良くなれたんだし、やっぱり感謝ね」
「俺、そんなにおっぱい感出してないと思うけど……。おっぱいきっかけで仲良くなる要素って何かあったか?」
「あら? 初めて会った時、私のおっぱいを凝視してたじゃない」
「……。ばれてたのか」
ちょっと恥ずかしがるような表情をしながら、そっぽを向いてしまった。
男の子って感じで、なんだか少し可愛い。
けれどそのまま、羽依里くんは立ち上がって海の方へと歩いて行った。
なにをするのかと思ったら。
「おっぱーーーーーーーーーーーーーい!」
あの時の私たちと同じように、彼もまたおっぱいと叫んだ。
これは……。
「パイリくんも、モヤモヤしてることがあるの?」
「ああ、俺も二人ともっと仲良くなりたいから、ちょっと言ってなかった話をしようと思ってさ」
「ふふっ♪ じゃあ聞かせてもらいましょうか」
「実は俺は、水泳部だったんだけどさ――」
「うんうん」
自分探しをしている紬。
自分のやるべきことを無くしてしまった羽依里くん。
自分を抑えてきた私。
自分を見失っていた私たちは、偶然にもこの灯台に集まってきた。
でも、それは必然なのかもしれない。
だってここは灯台なのだから。
船を導くことは出来なくても、ほんの三人くらいなら導けるかもしれない。
「そんなことがあったのね……」
「まあ。……軽蔑したか?」
「ううん、仲良くなれた気しかしないわ」
「そっか……ありがとな」
さて、灯台に導かれた私たちは、これからどこに向かうのだろう?
それは、きっと各々が決めることだ。
それがきっと、自分なんだと思う。
「それじゃあパイリくん。まだ誰にも言っていない、とっておきのお話をしてあげるわ」
「おお、聞かせてくれ」
「ええ。でも、そろそろ夕方だし……また明日にしましょうか?」
「え? 自分からふっておいてそれかよ」
「いいじゃない。だって……」
無駄な話と、意味のない時間を積み重ねて、を私たちの関係は深まっていく。
今後、私たちはどうなっていくのだろう。
それは、想像ができないけど……そんなに慌てることもないだろう。
だって……。
「夏休みはまだまだ長いんだし」
©VisualArt's / Key