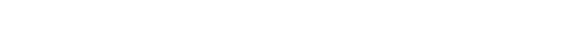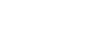「Summer Pockets」 ショートストーリー ~夏の眩しさの中で~【野村 美希 編】
<バランスは常に一定ではなく>
ドブにはまった。
夏休みの中頃。私、野村美希は街中でドブに片足を突っ込んでいた。
「まさかこんなことになるとは……」
なかなかの段差……スパッツでなければ、えらいことになっていただろう。
さて、もう片足もドブに突っ込まなければ、力を入れられそうもない。
両足をドブで汚すか、それとも誰か通りかかるのを待つか。
遠い目をしながらそんなことを考えていると。
「のみき……何してるんだ?」
「ん、鷹原か?」
鷹原羽依里。
夏休みを利用して、この鳥白島にやってきた青年。
わざわざ何もないこの島にやってきて、ブラブラしている変わった男。
まあ、裸になる奴や、卓球以外のことを考えられない奴よりはずいぶんマシだ。
それに、しろはや蒼、紬に水織先輩などといった、ちょっと難しい者たちからも信頼されているところを見ると、どうやら悪い奴じゃないらしい。
かくいう私も、それなりに信頼はしている。
「見てわからないか? ドブにはまっているんだ」
「えっと、趣味?」
「そんなわけないだろう。ちょうどいい、手を貸してくれ」
「ああ、わかっ――」
「なぜ顔を赤くする?」
「いや、だってパンツが見える」
「スパッツを履いているだろ?」
「どっちにしろスカートの中にあるんだろ? もうそれはパンツだ」
「ちがうぞ?」
「それに、水着の方が露出度も高いだろ?」
「水泳部にとって、水着はフォーマルみたいなものだし」
「独特の感性を持っているんだな?」
どうやら元々男子校にいたらしく、よく島の女の子と話すわりにこういうところはだめらしい。
正直、こういうところには好感が持てる。
「あ、とりあえずそこから出るのを手伝うよ」
「ああ、頼む」
鷹原の手を取り、ドブから片足を引っこ抜く。まあ、ドブというより側溝だ、それほど汚れてはいない。
「すまない、助かった」
「いや、別にいいけど。なんでそんなことになったんだ?」
「ちょっとバランスを崩してな、それでこのざまだ」
「ふらついたのか? 熱中症とかかも、気を付けないと」
「いや、単純にバランスを崩したんだ」
「そうか……にしても」
鷹原が、ジロジロと私を見てくる。
「なんだ? 人をジロジロと見るな。失礼だと習わなかったのか?」
「いや、それはゴメン。でもなんか、いつもと違う気がして」
「ほう、気が付いたか」
「女の子がちょっとでも変わったら、それに気付いてあげて、褒めるとモテるって聞いたことがあるんだ」
「なるほどな。しかし、そのジロジロと相殺されるだろ」
「そうかも……」
「まあ助けてもらった分、私の中の鷹原の株は上がった。それじゃあな」
「ああ、気をつけてな」
私は鷹原に背を向け、歩いていこうとするが。
「おっと!」
――ガボンッ!
「……」
「えええ……?」
ドブにはまった。
「のみき、何してるんだ?」
「いや、ちょっとバランスを崩してな」
「さっきも崩したんだろ? 本当に熱中症じゃないのか?」
「いや、そうではない……」
「でもフラフラしてるぞ? ちょっと水分とって、体冷やした方がいいって」
「本当にそれは大丈夫なんだ」
「とりあえず、ハイドログラディエーター改の水を頭にかぶってみたらどう…………ん?」
私のいつもと違うところに、やっと気が付いたようだ。
「ハイドログラディエーター改がない!?」
「やっと気が付いたか」
鷹原は不思議そうな目で私を見ている。
「そんなに珍しいか?」
「そりゃ、会った時から持ってるところしか見たことがないからな、すごく新鮮な姿だ」
「かも知れんが、普通に考えておかしいとは思わないのか?」
「なにが?」
「常に水鉄砲を背負ってる高校生の方が珍しいだろ」
「まあ……それはそうだけど」
ものすごく腑に落ちないという顔をしている。
「出先で置き忘れてしまったようでな、今は持っていないんだ」
「とりあえず、もう一度引き上げてもらえるか?」
「ああ、わかった」
鷹原の手を握り、ドブから抜け出す。
お互い、手をギュッと握っている。
「……」
ふむ……これはちょうどいいかもしれない。
「鷹原、頼みがあるんだが」
「ん? なんだ?」
「このまま手を繋いでてもらっていいか?」
「え!? いや、えっと……」
「まあ、別に嫌ならいいんだ」
「嫌じゃない! 嫌じゃないけど……」
「なんだ?」
「恥ずかしい……」
「乙女か……」
「男子校の人間は、乙女よりも恥じらいが強いんだ」
ものすごく挙動不審だ……。どうやらギャグで言っているわけではないようだ。
「っていうか、何で手を繋いだままにするんだ? もしかしてのみき、俺のことを好――……~~~っ!」
「恥ずかしがるなら余計な冗談を言うな」
「すいません……。で、何で手を繋ぐんだ?」
「ああ、バランスがとれなくてな」
「……?」
「ハイドログラディエーター改を装備してないと、私はバランスが取れなくなるんだ」
「ははっ、いやまさか。ヒゲを切られたネコじゃないんだから」
そう言いながら鷹原は笑う。
「いや、本当だ」
「え? マジで……?」
「信じられないか? だったら手を放して少し離れてみろ」
鷹原はコクリと頷いて、私から少し距離を取る。
私は歩いて鷹原のもとに向かう……が。
――ガボボッ!
「ええええ……?」
「見ろ、今度は両足でドブに落ちた。わざとこんなことをすると思うか?」
「思わない……。え、マジなのか?」
鷹原は手を差し出して、私をドブから引っ張り上げた。
結局、両足ともずぶ濡れになってしまった。
「そういうわけだ。すまんがよろしく頼む」
「わかった」
私は鷹原と手を繋ぎ、浜辺を歩く。
「この辺りにあるのか?」
「ああ。確か最後は、この辺りに置いたと思う」
「ちなみになんで?」
「裸を見ると反射的に撃ちそうになるんだ。浜辺で持っていると、罪もない裸を無差別で撃つ可能性があるからな。その予防だ」
「もはや病気だ」
「街中で裸になる奴がいるせいで、行動が沁みついてしまったんだ」
そんなことを話しながら、ハイドログラディエーター改を探す。
砂浜、岩場、浅瀬、鷹原に手を掴まれながら見て回るが……。
「見つからない」
「もしかして、波にさらわれたりとか……」
「波にさらわれた……だと?」
そうなってしまってはもう探しようがない。
しかし、それ以外考えられない……。
あれからずいぶん時間も経っているし、沖の方にまで流されたのでは……。
「ど、どうしよう、鷹原」
「――っ! ちょ、ちょっと待って」
鷹原は急に顔を真っ赤にして、私から視線を反らしている。
言ってしまえば照れているようだ。
「なんだ……?」
「いや、いつもだったら『私はどうすればいい、鷹原?』とかだろ? 何でそんなに弱気なんだよ?」
「だって……ハイドログラディエーター改がないんだぞ? ハイドログラディエーター改が!」
「ちょっとよくわからない……」
なぜわからないんだ!?
「ど、どうしよう……?」
「えっと、他に心当たりの場所は……」
「わかんない……」
「……弱気なのやめて。すごい動揺する」
「うん……がんばるけど」
「いや……なんかもう、普通の女の子みたいだ」
どこにいったんだ、ハイドログラディエーター改……。
あれがなければ、私は……。
「鷹原……もうちょっとだけ、頼らせてもらっていい……?」
「いいけど、ホント弱気やめて?」
「でも……どうしていいかもうわからない」
迷惑をかけている自覚はある。
でも本当に、どうしていいかわからない。

「えーっと、一旦冷静になるか」
「どうやって?」
「えーっと、天善に教えてもらった方法だけど、ワカメを頭にかぶるとか」
「わかった……かぶる」
「えー……?」
「ワカメ……取ってきてもらえる……?」
「いいけど……」
困ったような表情で、鷹原は海に入り、ブチブチとワカメを取ってくる。
私はそれを受けとり、早速頭にのせてみた。
「……」
「……」
「……何か言って」
「……ワカメと髪の色が似てるから、遠目からだと髪が伸びたみたいに見える」
「そう……、似合う?」
「どうだろう? ワカメだしな……」
……しかし、磯臭い。
この匂いを嗅ぎ、ワカメの冷たさを感じ……私はこう思うようになっていた。
「……何をしてるんだ、私は?」
「冷静になったな」
「ああ、すまない。弱気になっていた」
あまりにどうかしてる行動に、少し冷静さを取り戻した。
こんなことしてる場合じゃない、探しに行かなければ。
「鷹原、次の場所に行きたい。手を貸してくれ」
「ああ」
私は鷹原と手を繋ぎ、今度は住宅街を歩く。
「次はどこまで行けばいいんだ?」
「駄菓子屋だな。子供達が見つければ、きっと鑑定のために蒼の元に持ち込むだろう」
「おお、冷静になったおかげだな」
「認めたくはないが、天善には感謝しなければな」
「でも駄菓子屋かー……。手を繋いで行ったら、蒼に冷やかされそうだ」
「問題ない。事情を説明すれば、蒼もわかってくれるはずだ」
「っていうか、普段はどうしてるんだ? 学校とか、買い物とかでもハイドログラディエーター改を背負って生活してるのか?」
「そんなわけあるか。夏休み限定の現象だ」
「どういうことだ?」
「それはだな――」
鷹原の質問に答えようとした時のことだった。
「――あ?」
「ん?」
鷹原が黒髪の少女を見つけると小さく声を上げ、彼女もまた同じようにこちらを見つけ、不思議そうな顔をしている。
どうやら知り合いのようだ。
少女はスーツケースを引きながら、こちらに近づいてくる。
「エロいことする気だ!」
「しない!」
開口一番、なかなかすごいことを言ってきた……。
「鷹原、知り合いか?」
「うん、羽依里の知り合いだよ!」
「こんなに馴れ馴れしい態度なのに、位置は知り合いなのかよ」
「それじゃあ冒険仲間かな?」
「そうか。一応だが、もし鷹原に好意があったり、秘かに付き合っていたりしたら悪いから言い訳をさせてくれ」
「いや、そういう仲じゃないから」
「彼女が好意を持っているかもしれないだろ?」
「もしそうなら本人たちの前で言っちゃだめだろ?」
もっともだ。そこまで気が回らなかった。
「実は私は、ハイドログラディエーター改がないとバランスが取れなくなるんだ」
「ハイドロ?」
「ウォーターガンだ」
「ここに来るまでに数度ドブに落ちた。そこを助けてもらい、そして送ってもらってるんだ」
「おー……」
少女は少し考えこむ。
「浦島太郎的なことだね!」
「いや……ちがう」
どうしてそんな発想になる……。
「よくわかんないけど、ひげを失ったネコの様な状態なんだね?」
「ああ、その通りだ」
理解が早いのか遅いのか、よくわからない。
けれど、これで誤解を招くこともないだろう。
「そういうわけだ。またな、鴎」
「あ、二人ともちょっと待って」
「ん?」
鴎と呼ばれた少女は、私たちの前に立つと、スーツケースに座る。
そして親指を立ててグッとそれを立てた。
「ヘイ彼女ー! 乗ってく?」
「……どういうことだ?」
「なるほど、そういうことか……助かる」
「鷹原!? お前、理解しているのか?」
「アナタ、乗る。私、押す。羽依里も、押す。遠慮せずに乗っちゃってよ♪」
「いや、理解はできたが……いいのか?」
「まあ、よく乗ってるし、よく押してる」
「普段からこんなことしてるのか!? しかし、大切そうなスーツケースだ。乗ってもいのだろうか?」
「もちろんっ! ひげ猫団として、ひげのない猫は見逃せないよ」
「……ひげ猫?」
「まあ、そういうのがあるんだ」
「そうか、ではお言葉に甘える……。二人ともありがとう」
私はスーツケースに乗り、鴎と呼ばれる少女と鷹原に押されて前に進む。
「乗り心地はどう?」
「なかなかいいものだな。視点も変わって気持ちがいい」
「だよねー」
「ありがとう。本当に助かる」
「いえいえー。ところで羽依里」
「どうした?」
「二人で押すの、バランス難しくない?」
「確かに……一人の方が楽だったかもな」
「ねー」
三人でそんなことを話しながら、駄菓子屋の前へと到着した。
店の中では蒼が暇そうに外を眺めていたが、私たちの姿を見てこちらへとやって来た。
スーツケースに乗る私、それを押す鷹原と鴎という少女。
それを見て、鷹原に声をかけた。
「何あんた? のみきの奴隷にでもなったの?」
「ちがう。これにはちょっと訳があるんだ」
「ふーん? あれ? そっちの子は?」
「初めまして、奴隷二号です」
「おい! その流れだと、俺が奴隷一号みたいだろ」
「ちがうの?」
「俺は奴隷じゃない!」
「ってことは、もしかしてのみきが一号で、羽依里が……ご、ご主人様的な……」
「蒼?」
「はっ! きっとあたし、今から三号にスカウトされるのね!」
「すごい発想の子だ」
「きっとスーツケースの中には、いろんな形のものが……」
「いや、蒼。悪いが正気に戻ってくれ」
「っていうか、のみきに先越された!」
「撃つぞ?」
「ちょっと? 至近距離でそれは――……って、あれ?」
蒼は、いつもと少し違う様子の私に気が付いたようで、それと同時に妄想の世界から帰ってきたようだ。
「ハイドログラディエーター改は?」
「どこかに置き忘れた。ここに届いているかともったが……その様子だとないようだな?」
「そうね。今日はまだ、鑑定に来る子少ないし」
「そうか……」
ここに来れば何とかなると思ったのだが……。
思わずため息が出てしまう。
「あ、そうだのみき。灯台に行ってみるか?」
「……? 私は灯台になんて行っていないが」
「でもほら、紬がゴミ拾いしてるだろ? 海に落ちてたりしたら、きっと拾ってくれてる」
「なるほど! それは名案だ!」
ぬいぐるみやパリングルス、彼女は様々なものを拾っている。
ハイドログラディエーター改が落ちていれば、きっと拾ってくれているはずだ。
「よし、それじゃあ乗ってくれ」
「いや、灯台まではアップダウンが激しい、スーツケースは厳しいだろう」
「じゃあ歩いて行くか?」
「ああ」
「それじゃあ、私はここで離脱だね。ひげ、見つかるといいね」
「ひげを探してるわけじゃないが、ありがとう」
私は鷹原の手を取り、駄菓子屋を後にする。
「ええっ? 何であの二人、手を繋いでんの?」
「店員さん、それは私から説明しよう」
そんな声が後ろから聞こえてきていた。
灯台に続く道を、手を繋ぎながら歩く。
バランスを崩して、遠ざかろうとする私を、鷹原は引っ張ってくれて、そのたびに彼に密着をしてしまう。
「すまんな」
「いや……大丈夫だ」
「そのわりに挙動が怪しい」
「密着されると恥ずかしい」
「いや、じゃあやはりすまない」
「でも、男としては悪い気はしない」
「そうか」
男子校で女性に慣れていないが、それなりに女性に縁がある。
何とも生きにくそうな生態をしている。
「いっそのこと、初めから腕を組んだ方がいいだろうか?」
「それは……難易度が高い」
「そうか?」
試しに近寄り、腕を軽く組んでみた。
「……」
「……」
「すまない、確かに難易度が高い。さすがの私でもはじゅかしい」
「噛むほどだもんにゃ」
「お前もか」
腕を組むのはやめ、手を繋ぎ直す。
「お、鼻歌が聞こえてきた」
「では、紬は灯台にいるみたいだな」
「またからかわれたりするんだろうな……」
「まあ、私から説明するから大丈夫だ」
私たちは手を繋いだまま、灯台の元へと歩いていった。
「紬、ちょっといいか?」
「むぎゅ、ノムラさん! それにタカハラさんもです!」
「ああ、今ちょっと時間あるか?」
「はい、大丈夫ですよ。シズクも呼んできましょうか?」
「そうだな、頼む」
灯台には紬と一緒に水織先輩もいるようだ。
どうやら二人でヌイグルミを繕ったり、乾かしたりしているようだ。
「あら、珍しい組み合わせね? それに……」
「むぎゅ? どうしたんですか?」
「手を繋いでるわ」
「おー! おふたりは、仲良しなんですね!」
「そうね、仲良しなのね♪」
「いや、まあ……」
「まあ、悪くはないかな」
「それで、ごよーじは何ですか?」
からかわれたらからかわれたで腹が立つだろうが、それで済まされるのは、何というか少し腑に落ちない……。
まあいいが。
「実は、ハイドログラディエーター改が行方不明なんだ」
「あのごつごつした水鉄砲ね? でも、どうして灯台に?」
「もし波にさらわれていたりしたら、ここに流れ着くかと思ってな」
「紬、今日のゴミ拾いの中に、ハイドロはなかったか?」
「そですね。そういうものはありませんでした」
「そうか……残念だ」
「見かけたらお知らせします」
「ああ、頼む」
ここに無いとなると……あとは足で探すしかないか。
鷹原には迷惑をかけてしまうことになるかもしれない。
「落ち込んでるけど、そんなに大切なものだったの?」
「まあ、そうだな。あれがないとバランスが取れなくなるんだ」
「それ、どういう仕組みなの?」
「この夏は、常に大量の水を背負っていたからな。無くなった時にバランスが取れなくなるんだ」
「そういう理屈だったのか!」
「でも、そんな極端にバランスが取れなくなるものなの?」
「いや……静久、こう考えてみろ。片方のおっぱいがなくなるって」
「――!? そ、それは一大事ね! 確かに、バランスが取れなくなりそう……」
「そうだろ?」
水織先輩は時々、当たり前のように胸の話をすることがある。
けれど何故か、蒼や男連中はそれを認識していないふしがあった。
「紬……ちょっといいか?」
「むぎゅ?」
二人には聞こえないよう、紬に耳打ちをする。
(水織先輩だが、時々胸の話をしているように思うんだ)
(そですね。静久の話は、半分以上がおっぱいです)
(そんなにか!?)
(はい。ですが、わたしやタカハラさんには聞こえているんですが、皆さんにはおっぱいが聞こえていないみたいです)
やはりそうか。
(あとはカモメさんにもおっぱいは聞こえているみたいです)
さっきの少女か。
紬と鷹原はともかく、どうして私とあの子だけなんだ?
自分の胸に手を当てて考えてみる。
「……」
何となく理由が理解できた。
まあいい……。
耳打ちをやめて、二人にも聞こえるように先ほどの話を続けることにした。
「そういうわけで、まっすぐ歩けなくて困っているんだ」
「そう、まるでひげの無いネコね」
「とてもかわいそうということですね」
「ちがうぞ」
「あ、もしかして、それが原因でパイリくんと手を繋いでたの?」
「そうだな。鷹原には悪いが、頼らせてもらっている」
「仲良しだからではなかったんですね」
「そうだな」
「え?」
鷹原がさみしそうな顔をしている。
「いや、仲がいいことを否定したわけじゃないぞ? 頼らせてもらっているし、信頼もしている」
「そ、そっか……」
今度は照れている。
蒼もチョロいと思っていたが、こいつもこいつで似たようなところがあるな……。
「ふふふっ♪ やっぱり仲良しなのね」
「あの、ノムラさん。バランスがとれないというのであれば、こういうのはどうでしょう?」
「ん? なんだ?」
「片側に重りをもって歩くんです」
「まあ……悪い発想ではないが、いったい何を持って歩く?」
「ノムラさんには、こちらをお勧めします」
紬はタタタッとベンチの方に向かうと、何か大きなものを持ってきた。
「あら、さっき修理して、ベンチで乾かしてたワニのヌイグルミね?」
「はい、メガネカイマンのパリーちゃんです」
「これずいぶんデカいな」
「ハナガラサラマンダーのナガラさんと同じくらい大きいです」
「か、かわいいじゃないか……パリーちゃん」
「ノムラさん、気に入っていただけましたか?」
「あ、ああ……。持って帰ってもいいのか?」
「いいですよ、かわいがってあげてください」
「あ、ああ。ありがとう!」
「シズクが綿を追加してくれたので、むぎゅ~ってすると気持ちいいですよ」
「わにゃ~……」
「ちなみに、おっぱいと同じ柔らかさに調節したの。パイリくんも触ってみる?」
「そう言われて触れる男はなかなかいないと思う」
「帰ったら、ぜひむぎゅむぎゅさせてもらう」
「はーい。それでは、気を付けてお帰り下さい」
私と鷹原は、紬と水織先輩に見送られて灯台をあとにした。
いや、忘れてはいけない。パリーちゃんも一緒にだ。
パリーちゃんを小脇に抱え、私たちは灯台から町への道を歩いていく。
「バランスはちゃんととれてるか?」
「ん、さっきよりはずいぶんマシだが、まだ少しふらつくな」
さすがにドブには落ちないだろうが、まっすぐ歩いているつもりでも微妙に曲がっていく。
高い段差がある場所もあるし、少し危ないかも知れない。
「鷹原、手を繋ぐほどではないが少し不安だ、掴まってもいいか?」
「ああ、もちろんだ」
私は鷹原の袖をつかみ、ゆっくりと彼の後をついていく。
しかし……いいものをもらった。思わず顔がほころんでしまう。
いやいや、迷惑をかけている身で、ニヤニヤはしてられない。
顔を見られないよう、少し俯いて歩こう。

「しかし鷹原、パリーちゃんはどこに飾ればいいと思う?」
「玄関に置いて、トラの敷物みたいにするのは?」
「なるほど、ワニに出迎えてもらう生活か……それは癒しだな」
「え? 採用……?」
「いや、まだ採用ではない。この大きさなら、抱き枕のように使うこともできるだろう」
「食われそうだ」
そんなことを話しながら歩いていく……。
踏んでしまったら可哀想だから、やはり玄関はやめておくべきか……。
「おー! 羽依里にのみきー! 何してんだ?」
「良一、邪魔してやるな、ダブルスの最中のようだ」
「どこに卓球台があんだよ……? で、何してんだ、羽依里?」
「ああ、ちょっとのみきと探し物をしててさ」
「へー、何さがしてんだ? っていうか、のみきはさっきから何で黙ってんだ?」
「……」
玄関か……抱き枕か……。
いかん、また顔がほころんできた。
「お、おいおいおい! 羽依里の袖をギュッとしながら、笑顔で俯いてるぞ!」
「しかも、プレゼントらしきヌイグルミも持っているな」
「待って、変な誤解をし始めるなよ?」
「鷹原はのみきと付き合っているのか?」
「言ったそばから!」
「羽依里……こいつ、ちょっと乱暴な奴だけどさ、すげーいい奴だから、ちゃんと頼むな」
「そういうんじゃないから」
うん、やはり玄関だな。帰ったらワニ……いい生活じゃないか。
「のみきも、少しは何か言ったらどうだ?」
「ん、ああ。えへへ……ふふっ。そうだな」
「うおーーー!? なんか女の子っぽい反応してるーーー!」
「鷹原、幸せにしてやってくれ」
「ちがっ! ちょっと、のみきさん!?」
だがやはり……抱き枕も。しかし、熱帯夜が続いている事を考えると。
「もし抱き付いて寝たりしたら、迷惑だろうか? 鷹原、意見をくれないか?」
「えっ?」
「――っ! い、いや……なんか俺たち、聞いちゃいけないこと聞いたな」
「すまん。そこまでの関係だったとは知らず……」
「いや、謝るな! なんか誤解があるんだと思う! 俺もわかんないけど!」
「ふふっ……これから、楽しくなりそうだな」
「のみき!?」
「お、おお……じゃあ俺は秘密基地に戻るかな」
「俺も、特訓があるからな」
「おおおお! 誤解したまま行くな!」
少し止まっていたようだが、私たちはまたゆっくりと歩きだした。
「さっき、良一と天善の声が聞こえた気がしたが、気のせいか?」
「え? 全く気付いてなかったのか?」
「そうだな。ハイドログラディエーター改がないせいで、裸センサーが反応しなかったのかもしれん」
「なんだ裸センサーって」
「ところでさっきの質問の答えはまだか? パリーちゃんに抱き付いて寝たら、暑いし迷惑なのかどうか」
「熱帯の動物だし大丈夫じゃないか?」
「なるほど。盲点だった……やるじゃないか鷹原」
「う、うん」
しかし、これだけ探しまわっても、ハイドログラディエーター改が見つからない
やはり波にさらわれ、どこかに行ってしまったのだろうか?
一縷の望みを託し、二人で海沿いをずっと歩いて探す。
やがて、砂浜から港、テトラポッドや岩場のある方にまでやってきた。
「……あ」
「ん、しろはか?」
どうやらここは彼女の釣り場らしく、少し困った顔でこっちに視線を向けていた。
最近は人を避けてるようだし、あまり邪魔してしまっては悪いだろう。
「行こうか、鷹原」
「あ、ちょっといい?」
こいつ、普通に話しかけた……。
「ん、少しくらいなら」
しろはも普通に答えた。
「のみきが今、ハイドログラディエーター改を無くして困ってるんだ」
「……。名前、カッコイイね」
「あ、ああ。ありがとう。しろははこのセンスをわかってくれるんだな」
「うん。そっちのぬいぐるみは?」
「ああ、こっちはパリーちゃんだ」
「普通だね」
「もらいものだからな」
「でさ、ハイドログラディエーター改が無いせいで、バランスが取れなくてまともに歩けないみたいなんだ」
「……どういう仕組み?」
「この夏、あれ持って走り回ってたせいで、ハイドロ筋が発達したらしい」
初めて聞く単語だ。
「うん、大体わかった」
……わかったらしい。
「それで、私に何の用?」
「見かけたら連絡が欲しいんだ」
「わかった。もし見かけたら……――っ!?」
「どうした?」
しろはは、急に視線を海に向け、グイっと竿を後ろに引いた。
「アタリの気配がする」
「何か釣れそうなのか?」
「う、うん……ちょっと待ってて」
しろははそう言って、リールを急いで巻き上げる。
すると……。
「えっと、もしかしてこれって」
しろはが釣り上げたのは。
「ハイドログラディエーター改!」
私たちの目的のものだった。
「ありがとうしろは、おかげで助かった」
「ううん。でも、どうして魚以外のものばかり釣れるんだろう……」
私はしろはからハイドログラディエーター改を受け取り、肩にかける。
パリーちゃんは、両手で抱きしめ、左右のバランスがとれるようにした。
「それじゃあ帰るか?」
「そうだな。鷹原、今日はありがとう」
「いや、気にしないで。見つかってよかったな」
今日、何度も繋いだ手を今一度とり、私たちは握手を交わす。
そしてその手を放して一歩踏み出すと。
「あ……れ……?」
目の前の景色が横になって……。
じめんが……ちかづいて……。
「のみき!?」
めのまえが……まっしろに……。
「……すまんな、鷹原」
「いや。落ち着いたか?」
「ああ……」
気が付けば私は、鷹原の部屋で横になったいた。
暑い中を歩き回ったせいか、軽い熱中症になってしまったようだ。
あの場で倒れてしまったものの、パリーちゃんがクッションになったおかげで、特にケガはなかった。
「鷹原、今日はずっとすまなかった」
「いや、どうせ暇だし別にいいよ」
「これ以上迷惑かけるのも悪い、そろそろお暇するとしよう」
「いやいやいや、もう少し休んでけって」
「しかし……」
「親御さんと離れて暮らしてるんだろ? 何かあったら大変だし」
「しかし、これ以上甘えるわけには」
「いや、別にそんなの気にしないからさ、存分に甘えていけって……」
「なるほど……。では鷹原が甘えさせてくれるというわけだな?」
「その言い方……意識しちゃうからやめて」
「ふふっ。ああ、わかって言っているからな」
私がそう言いながら笑うと、鷹原はバツが悪そうに笑った。
何とも面白い奴だ。
「鷹原」
「ん?」
「この夏……この島に来てくれてありがとう」
「どうした急に」
「いや、島のみんなが楽しそうだからな。しろはのあんな態度は久しぶりに見た」
「そっか……楽しいって思ってくれてるんなら、来たかいがあったな」
「もちろん、私も楽しいと思っている」
「だから……意識しちゃうから」
「まあ、そういうわけでお前には感謝している」
私は言葉を続ける。
「だから、鷹原にも島を楽しんでほしい。私の面倒なんて見ずに、遊びに行ってきてくれ」
そうい言うと、鷹原は照れたように窓の外に顔を向けた。
「いや、まあ……あんまりゆっくりのみきと話すこともなかったから、これはこれで楽しい」
そして無理やり作ったような、いつもの顔でこちらを向きなおしてきた。
「だからまあ、これも島を楽しんでるってことで」
「そうか……。楽しんでくれてるならいいんだ」
私は少し力を抜いて、加藤家の天井を見ながら、吹き出すように軽く笑った。
気を使ってくれているのか、それとも本音なのか、どちらにせよ嬉しい言葉だった。
「では、もう少し休ませてもらう。もし寝てしまったら適当な時間に起こしてくれ」
「ああ、寝る前に麦茶飲んどけ」
返事をして体を起こし、軽く水分を取って、私は再び横になった。
「のみき……家に帰った後もさ、もし体調悪くなったら呼べよ?」
「ん、なんだ? 来てくれるのか?」
「ああ、どうせ暇だから、いつでも行ける。まあ、役に立つのかは怪しいけど」
「そうか……」
私しかいない、あの部屋に鷹原が来ることを想像してみる。
「……」
……なるほど。
「だったら体調を崩すのも、たまには悪くないかもな……」
何かほんの少し、私の心のバランスが、誰かに傾いたような気がした……。

©VisualArt's / Key