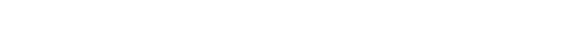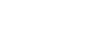「Summer Pockets」 ショートストーリー ~夏の眩しさの中で~【加納 天善 編】
<卓球道、その始まり>
「ふっ……! ふっ! ふっ! ふっ! はあっ!」
10㎏の重りを付けたラケットの素振り千回を終わらした頃。
秘密基地の隙間だらけの壁から、光が差し込んでることに気づく。
朝日のようだ。
「……また徹卓をしてしまったか」
眼鏡を外し、額から伝う汗を拭う。
卓球台に置いておいた水を一口含んでゆっくりと飲み込む。
すでに常温となっていた水は、それでも特訓で熱くなった体によく染みる。
1度家に帰るか。
いや……、帰ってしまうとそのまま眠ってしまうだろう。
そのくらい体を痛めつけている自覚はある。
「それでも届かない場所がある……遠い物だな」
いや、もしかしたら今の俺ならば……
秘密基地の奥にしまっておいた俺と良一の玩具箱を引っ張り出す。
ミニ四駆やハイパーヨーヨー、修学旅行で買ったヌンチャク……そんな子供時代の思い出のさらに下にある古びたラケットを手にする。
普段使っているシェークハンドとは違う形。
ペンホルダーと呼ばれる、昔ながらのラケットだ。
それも片面だけにラバーが貼られている、日本式。
今ではもう、これを使う選手もそう多くはない。
だが、俺はこのラケットを使っていた「奴」には勝てないままだった。
日ペンラケットを握る。
親指と人差し指を使った、文字通りペンを持つような握り。
久しぶりなのに、どこか馴染む感触だ。
俺の原点もまたこのラケットだったのだから当然かもしれない。
ピンポン玉を高く上に投げて、サーブをする。
「必殺! ドラゴンスレイブ!!」
強烈なフォアハンドでの打球。
強烈なトップスピンが空気との摩擦を生み、まるで龍の咆吼のような音を上げる。
が、相手コートには落ちず、真っ直ぐ秘密基地の入り口に伸びていく。
パッカーーーン!!
「ぎゃあっ!」
ちょうどやってきた鷹原の額に軽快な打撃音を与えた。
「顔面セーフか」
「アウトだ! つーか今のなんだよ! なんで遊びに来てそうそうピンポン玉をぶつけられるんだ! 帰れってことか?! 俺メンタルそんなに強くないから泣きながら帰るぞ!」
額にピンポン玉と同じ大きさの赤い腫れを作った鷹原が批難めいた声を上げた。
「すまない、悪気があったわけじゃない。ただ……」
「ただ?」
「避けられないお前が悪い」
「悪びれろよ!」
「だからすまないと言ったが?」
「後に続く言葉で台無しだ!」
鷹原はこの夏休み、加藤のおばーさんの遺品整理の為に島にやってきた都会の人間。
何かワケアリのようだが、そこは深く訊いていない。
誰にでも人に話したくないことは、1つや2つあるものだから。
「つーか、さっきの奥義、新しかったな? 初めて聞いたぞ」
彼はよく俺の特訓に付き合ってくれている。
だから、今の技に違和感を覚えたんだろう。
「あれは奥義じゃなく、必殺技だ」
「……? 違うのか? 確かに必殺って言ってたけど、なんか子供っぽいな」
「当然だ」
俺は日ペンラケットを見つめて呟く。

「子供の考えた技だからな」
「……? ワケアリ、なのか?」
「そんな大仰なものじゃない。だが……」
このタイミングでやってきた彼に何かしらの意味があるとすれば。
語ってみても良いのかもしれないな。
俺は鷹原を真っ直ぐ見つめる。
「少し話を聞いてくれないか」
「お、おう?」
「俺がどうして、卓球をしているのかを」
「おお、それは興味があるな。おまえがここまで卓球にのめり込んだ理由って気になっていたんだ」
「そうか」
屈託無く笑う鷹原から視線を外し、俺は再度手にしていたラケットを見つめる。
「ある男の子の話だ」
「うんうん」
「そいつは子供の頃から内気で……ひ弱で」
「うん……うん?」
「体育の時間に誰かと二人組になるのも恥ずかしがるような奴だった」
「待って」
鷹原がこっちに手の平を向けて、俺の言葉を遮る。
「どうした?」
「その話のくだり、聞き覚えがある。いや、ちょっと違うんだけど……確認するが、これって良一の話じゃないよな?」
「違う。俺の話だ」
「そうか……、話の腰を折ってごめん。続けて」
「ああ、どこまで話したかな……確か、そうだ、彼女は手の届かない、遠くに行ってしまったんだ」
「待って」
また鷹原が手の平を向けて、言葉を遮った。
「跳んでる。すごい間が跳んでるうえに、かなり重要なネタバレも食らった」
「む? そうか、語りたいという気持ちばかりがはやってしまったようだ」
「体育の時間に誰かと二人組になるのも~、ってとこまでしか話してないから」
「そうだったな、すまない。とにかく彼は、内気でひ弱で恥ずかしがり屋だった」
俺は昔を懐かしむように目を閉じる。
「小学校に図書室があってな。夏休みも、外で遊ばずにそこに入り浸って本を読んでいるような奴だった。友と呼べるような奴もいなかった」
ふと見ると、鷹原が頭を抑えながら唸っていた。
「どうかしたか?」
「うー……うん、まあいいや。続けて」
「ああ、そこで女の子と知り合ったんだ。似たように、内気で本が好きな子だった」
「少しだけ、話すようになったんだな、本の話とか。で、ひそかに友達だと思っていたんだろ?」
「その通りだ。……話したことがあったか?」
「いや、気にしないで」
「とにかく、俺は少しだけ学校が楽しいと思えるようになってきた」
俺は記憶にある小学生時代を深く思い出す。
あの日も――、俺と彼女は図書室の奥の席で、向かい合わせに座って本を読んでいた。
「ねえ、加納くん」
不意に呼びかけてくる声に、返事をしないで顔だけを上げる。
「本読んでるだけだと退屈じゃない?」
「でも、図書室は本を読む場所だから……」
「そうだけど、折角一緒にいるのに、ちょっと勿体ないよね」
彼女は周囲を見回してから、声を潜めて言ってくる。
「いけない事、しちゃわない?」
「いけない事? それはしちゃいけない事だからしない方がいいんじゃないか?」
「そうなんだけど、だから楽しくなるんじゃないかと思って」
「……何をするんだ?」
俺が話に乗ってきたことが嬉しかったのか、彼女はこれまで見せたことがないような笑顔になった。
そして、鞄の中から筆箱をとりだし、さらにその中の消しゴムを手に取った。
「えへへ、消しゴム落とし」
それは学教の休み時間、男子たちが賑やかにしているゲームだった。
ルールは単純で、机の上で自分の消しゴムを指で弾いて、相手の消しゴムを机から落とすだけ。
自分たちの実力で遊ぶクラスを決め「プロ級」は消しゴムを落とされたらその消しゴムは、落とした相手の物になるというシビアなもの。
中には新品の消しゴムを一回の試合で奪われて、泣きべそをかく奴もいた。
内気な俺は、とてもじゃないけどそんな賑やかな場に混ざる事なんてできなかった。
それでも、楽しそうだなと……離れた場所から見ていた。
それは彼女も同じだったんだろう。
だから、俺の心は躍った。ずっとやってみたかったゲームだから。
「わかった、やってみよう」
俺も筆箱から消しゴムを取り出して、机の上に置く。
「でも、静かにな。ここは図書室なんだ」
「もちろん。いけない事はこっそりするから楽しいんだもん」
彼女はウィンクをしながら自分の消しゴムを机に置いた。
「消しゴム落としか、懐かしい遊びだな」
鷹原が懐かしむように言った。
「都会でもやっていたのか?」
「あれは小学生なら、誰でも通る遊びじゃないか?」
「なるほど、都会だろうと島だろうと子供の頃はみんな同じということか」
「ああ、でも俺たちは指で弾かなかったな」
「ならどうやって消しゴムを動かしていたんだ?」
「ノック式のボールペンの、上の部分で弾いてた。中のバネを二重にして威力をあげたり見えない部分で改造とかしてたんだ」
「メカニック級か」
「鳥白島ではそう言うのか?」
「一部の金持ちたちに許されたクラスだ。主に徳田やその取り巻きがやっていた」
「あー、徳田スポーツのあいつか」
「とにかく、そんなささやかな遊びが楽しかったんだ。みんなが普通にしていたことが俺たちにはできなかったからな」
そこまで言って、俺は唇を噛む。
「だが、それも長くは続かなかった……」
「何があったんだ?」
鷹原の問いに、俺はまた遠い目をして幼い日の事を思い出す。
学校の机よりも広く、天板につや出し加工を加えられていた図書室の机は消しゴム落としを白熱させた。
少しの力でも良く滑り。
学校でみんながやっていた物よりも楽しく見えた。
いや、楽しかった。
だから、二人とも夢中になりすぎた。
「くらえーーー! ドラゴンスレーーーイブ!」
「ぐわああああーーー! 俺の消しゴムが真っ二つにーーーーー!」
「図書室では静かにしなさい!!!」
図書室を管理している先生にめちゃくちゃ怒られた。
「俺たちは泣きそうな顔になりながら、二人で謝った」
「そりゃ図書室で叫んでたら怒られるわ。って、ドラゴンスレイブがここで出てきたか。消しゴムが真っ二つってどういう技? 本当に消しゴム落としか?」
鷹原が呆れ半分、興味半分といった顔で訊いてくる。
「子供の遊びだ。必殺技の名前を叫べば強くなれるような気がするだろう」
「いや、でも消しゴムが真っ二つになったんだろ?」
「一定以上の力が加われば、消しゴムなんて簡単に折れるだろ。つまりはそういうことだ」
「ん? んんー……? そういうものか?」
俺の説明に鷹原は納得していない顔だ。
「とにかく、俺たちの消しゴム落としはこれで終わってしまったんだ。そしてまた二人で本を読む日が続いた」
俺は記憶にある小学生時代をまた深く思い出す。
あの日も――、俺と彼女は図書室の奥の席で、向かい合わせに座って本を読んでいた。
「ねえ、加納くん」
彼女の声に、返事をしないで顔だけを上げる。
「本読んでるだけだと退屈じゃない?」
「図書室は本を読む場所だし、前にうるさくして怒られたばかりだろ」
俺は声を小さくして答える。
「そうだけど、折角一緒にいるのに、ちょっと勿体ないよね」
彼女は周囲を見回してから、声を潜めて言ってくる。
「またいけない事、しちゃわない?」
「消しゴム落としはもうしないぞ」
「もっといけない事」
彼女はそう言って、カバンからいくつかのビー玉を取り出した。
「これなら、少しの力で机の上を転がるから、静かに対戦できるよ」
俺は気づくべきだった。
彼女は“もっと”いけない事だと言っていた。
つまり、消しゴム落としよりも、いけない事だったんだ。
だけど俺は、彼女の提案するゲームの方が気になっていた。
楽しそうに思えたんだ。
「……1回だけなら」
そう答えた俺に、彼女は本当に嬉しそうな笑顔を向けてくれた。
ビー玉対決は、あっという間に白熱した。
「くらえーーー! ドラゴンスレーーーイブ!」
「ぐわああああーーー! 俺の爪がーーーーーーー!」
「図書室では静かにしなさい!!!」
図書室を管理している先生にめちゃくちゃ怒られた。
「俺たちは泣きそうな顔になりながら、二人で謝った」
「またドラゴンスレイブが出てきたぞ? 消しゴムを真っ二つにする技じゃなかったのか?」
「俺の爪が真っ二つになった」
「ああああああーーー! 痛い痛い! 想像させるな!」
「ともかく、俺たちはまた先生に謝った。特に俺は泣きながら謝った」
思い出すだけであの頃の痛みが蘇る。俺はそっと右手の人差し指を握った。
「次、騒がしくしたら、出入りを禁止するとまで言われてな」
「そりゃそうだわ」
「だから、おとなしく本を読むことにした。だが彼女は再度言ってきた、本読んでるだけだと退屈じゃない?と」
「その子、学習能力ないのか?」
鷹原が明らかに呆れた顔をしていた。
「ああ、全くの同感だ。もちろん、俺は断った。消しゴム落としも、ビー玉転がしもしないと……だが……」
「だが?」
「彼女が俺に見せてきたのは、古びたピンポン玉だった」
「あ、ここでようやく卓球に繋がったか」
「ふっ……卓球などと呼べるようなものじゃなかった。ルールさえろくに知らなかったんだからな」
俺はあの時のことを思い返すように、自前のピンポン玉を握った。
「広い机をコートにして、ネットの代わりに本を立てて、ラケットの代わりに本を使った」
「……図書室で考え得る限り最悪な遊びだな……」
「ああ、白熱した」
コン……カコン、コン、……カコン
「加納くん、打ち合いが続くようになってきたね」
「ああ、よく分からないけど、気分が良い」
「じゃあ、少しだけ本気だすよ?」
「望む所だ」
「くらえーーー! ドラゴンスレーーーイブ!」
「あああああああーーーー! 先生の眼鏡が真っ二つにーーーー!」
「俺たちは、走って逃げた」
「最悪っていうか、最低だな……」
「ふっ……若さ故の過ちだな。こうして俺たちは図書室という憩の場を奪われてしまった」
「いや、完全に自業自得だろ。なんで被害者ぶってるんだよ」
「けれど、転機というのはどこで訪れるのかわからないものだった」
「……?」
「翌日、俺たちは職員室に呼び出された。そこで言われたんだ、卓球をやらないか、と」
捨てる神有れば拾う神有り。
俺たちのラリーを見て、可能性を感じたと言う者が現れた。
誰かから認められるというのは初めての事で、戸惑いしかなかった。
だけど、自分たちを見てくれている人が居たということが嬉しくて。
俺と彼女は、二つ返事で承諾した。
俺たちの居場所は、図書室から体育館へと変わったんだ。
学校の体育館では、島民たちのレクリエーションとして卓球が行われていた。
年寄りたちや、主婦たちが楽しそうにピンポン玉を打ち合っていた。
山なりの軌道でゆっくりとした卓球を楽しんでいる者。
筋肉に任せて、直線的な弾道で打ち合いをしている者。
ただ、総じてみんな笑顔だった。
「ふわーー、これが卓球かー」
「俺たちがこんな場所にいてもいいんだろうか」
「誘われたんだからいいんだよ。はい、これラケット」
「四角くて持ちにくいんだな」
「ペンホルダーっていうらしいよ」
彼女は親指と人差し指でわっかを作って、ラケットを握ってみせる。
俺もそのマネをしてラケットを握った。
意外としっかりと手に固定できる。
「卓球、知ってたのか?」
「ううん、ちょっとだけ先に勉強してみたの。加納くんに教えてあげようと思って」
「……俺に卓球なんてできるんだろうか?」
「物は試し、図書室でやってた交互に打つやつ、やってみよ」
「ウォーミングアップだな」
「うん」
初めて立つ卓球台。ネット越しに見える彼女の姿。
目に映る物全てが初めてな物ばかりで、胸がときめいた。
「いくよー」
「こい!」
「くらえーーー! ドラゴンスレーーーイブ!」
「そう来ると思ったぞ!」
彼女の行動を読んでいた俺は、真っ直ぐ飛んでくるピンポン玉を的確に打ち返した。
ピンポン玉を打ち返す時の心地よい音。
腕から体まで伝わる小気味よい衝撃。
何かに目覚めたような気分だった。
いや、ずっと欠けていた何かがカチっとはまったような気分だった。
「やるね、加納くん! たーーーーー!」
「なんの! まだまだっ!」
カン! カン! カン! と、ピンポン玉をラケットでお互い打ち返し続ける。
だが、やはり俺たちはまだきちんとルールを理解していなかった。
ピンポン玉を卓球台にバウンドさせること無く、ただ打ち返しているだけだった。
やっていることは卓球の道具を使った羽子板。
だけど、そんな打ち合いを島の大人達は面白そうに見ていた。
──まずは楽しめ。
そう、教えてくれた。
その楽しさの中に、競技としてのルールを加えていく。
サーブを打つときは、まず自分のテーブルでワンバウンドさせること。
ピンポン玉を打ち返すのは、自陣でワンバウンドしてから。
ただ打ち返していただけに比べて、考えながら打つことが増えていった。
だけど、バウンドさせなければいけないことを、マイナスで無くプラスで考えることも教えて貰った。
ピンポン玉に強烈な回転を加えることで、バウンドした後の方向を変化させることが出来る。
そうなれば、次はどのくらい回転を加えるかという駆け引きも生まれる。

「必殺! ドラゴンスレーーーイブ!」
「くっ!!」
彼女の放つあり得ない曲線軌道のドライブスマッシュは、バウンドする度に違う方向に飛んでいく。
どうしても俺のラケットでは捉えることが出来なかった。
「ふふーん、これで98連勝! まだやる?」
「と、当然だ!」
才能と言う奴だろうか。
正しいルールで卓球を始めてから、俺は彼女に1度として勝つことが出来なくなっていた。
「たーーーー! ドラゴンスレーーーイブ!」
「ぬおおおおおお!」
「はい、99連勝ーーーー!」
「も、もう1戦! 頼む!」
俺はラケットを握りしめながら、彼女に頭を下げる。
「うーん、でもちょっと疲れちゃったかな」
「ならばこそのチャンス!」
「うわ、そこは全力のお前を倒してこその勝利の価値とかじゃないの?」
「勝つ為に最善を尽くすのが礼儀だろう」
「格好いいセリフだけど、かっこ悪い」
彼女はやや引きつった笑みを浮かべていた。
「ちょっと休憩しない?」
「わかった。だが、お前の体力が回復しきらない程度で頼む」
「あはは、本当に勝つのに必死だね」
彼女は笑いながら、その場にペタンと座った。
呼吸を整えるようにゆっくりと大きく息を吸う。
「加納くんはやっぱり男の子だね。最近、体力の差を感じるよ」
「俺はただ負けたくなくて1人で特訓をしているだけだ」
「そうだね、だけどやっぱり男の子と女の子じゃ、決定的な差があるよ」
「だが、俺はまだおまえに勝てていない」
「私も必死だから。加納くんに負けたくないって気持ちで一杯なんだよ」
勝ちたい気持ちと、負けたくない気持ち。
どちらの方が勝利に結びつくのだろうか。
少なくとも、俺が勝てていない以上、負けたくない気持ちの方が強いのかもしれない。
「ふふ、くすくす」
「どうしたんだ? 急に笑いだして」
「ううん、なんだか不思議だなって思って」
彼女は遠くを見つめるような目で体育館の外を見た。
「図書室にしか居場所がなかったはずなのに、こんなに体を動かして楽しい気持ちになれてる」
「ああ、それは俺も同じだ」
「加納くんと一緒だから、楽しいのかな」
そう言った彼女の顔は少し赤かったように見えた。
だが俺は、彼女の言葉に戸惑いすぎて、きちんと顔を見ることが出来なかった。
素直にもなれなかった。
「俺は、負けてばかりで楽しいとは言えない」
そう答えることで精一杯だったんだ。
だけど、この胸の高鳴りはなんだろう。
この子と一緒に居るときは、いつもの自分とは違う自分でいる気がする。
変に強がって、無理に格好いいところを見せたいと思ってしまう。
「私、加納くんともっと色々な事がしたいな」
「色々な……事?」
「消しゴム飛ばしから始まって、ビー玉転がしをして、今はこうやって卓球を一緒にしてる」
「そうだな」
「もっと、加納くんと……コホコホ……」
「……? どうした?」
「ううん、なんでもないよ。それより勝負は明日ね」
「なに?」
彼女は立ち上がると、深呼吸をする。
「実は今日はちょっと用事があるの。だから勝負は持ち越しで」
「わかった。全力のお前を倒してこその勝利の価値だからな」
「それ、もっと早くに言わないと」
呆れたように、彼女は肩をすくめる。
だけど、すぐに真っ直ぐ俺を見つめた。
「……あのね、加納くん、私が100勝したら聞いて欲しいことがあるの」
「次の1勝は俺が貰うから難しいかもしれんな」
「あー、言ったなーー」
彼女が笑い、俺も笑った。
俺たちは確かに友達で、そしてそれ以上の繋がりを感じていた。
「でも、俺は……気づいてやれなかったんだ」
未だに俺はあの時のことを悔いている。
無理にでも試合をしておくべきだった。
「何があったんだ?」
俺の声が沈んでいることに、鷹原は心配そうな顔をする。
「翌日、俺は体育館で彼女が来るのを待っていた。だが、来なかった」
「来なかった?」
「その次の日も、そのさらに次の日も。俺は彼女が来るのを待ち続けた」
「彼女に何があったんだ?」
「言っただろう。彼女は手の届かない、遠くに行ってしまったんだ。もう、この世界に彼女はいない」
俺は窓の外を見ながら、呟くように言う。
「結局……、俺は彼女から1勝することは叶わなかった」
「だからなのか?」
「何がだ?」
「それ以来、ずっと卓球を続けて、いつか彼女に名前が届くようにって」
「そうだな……、届くといいな」
窓の外の、さらに遠く──、空を見上げる。
鷹原も察してくれたんだろう、それ以上は踏み込んでこようとはしなかった。
「おーっす、と、おっ? 羽依里ももう来てたのか」
手に何かを持った良一が秘密基地に入ってきた。
「良一? 何を持ってるんだ?」
鷹原が良一が持っている物を指差して訊ねる。
「へへ、ラジオだ。折角だからここで聞こうと思ってな」
「何かのニュース?」
「いーや、試合だ」
鷹原の問いに、良一はラジオの電源を入れる。
チューナーのバンドをあらかじめ合わせていたのか、すぐに音声が聞こえてくる。
『ドラゴンスレーーーーーイブ!』
「なぬ!?」
ラジオから聞こえてきた音声に、鷹原が素っ頓狂な声を上げる。
『全日本女子テニス大会、決勝戦、1セット目をストレートで先制したのは斑鳩麗選手!』
「は~、麗のやつ絶好調だなー」
「え? 知り合いなのか?」
「麗はこの島出身で同い年なんだけど、すでにプロのテニスプレイヤーなんだ」
「へえ、鳥白島出身のプロテニスプレイヤーか」
「小学校の時に親の都合で急に引っ越しちまったんだけどな。ああ、転校直前までは天善と卓球やってたぜ」
「へえー……え?」
「結構なドジッ子でさ、親と本土に遊びに行くと思ってたら実は引っ越しだったってオチよ」
良一の説明を聞いた鷹原がいぶかしげな顔で、俺の方を見る。
「ひょっとして……天善、さっき話していた彼女って……」
「言ったはずだ。もう、この卓球界(せかい)に彼女はいない、と」
「紛らわしいわ! 意味深な咳はなんだよ! 卓球やってたのに何でテニスなんだよ!」
「愚問だな。消しゴム落とし、ビー玉転がし、卓球、セパタクローとくれば、次はテニスに移行してもおかしくない」
「今おかしいのが間に入った! 彼女、本土に渡ってから何してるんだ? なんでタイの国技? つーか! すっげー初恋みたいな流れだったじゃねえか! 勝ったら告白みたいな感じだったじゃねえか!」
「そうだな、あの当時ならそうしたかもしれんが……、今は無理だ」
俺は深くため息を吐く。
そんな俺の仕草に、鷹原は目を細める。
何かに気づいたように。
「やっぱり、勝てなかったから、なのか?」
「いや」
俺は静かに、でもしっかりと首を横に振る。
そして鷹原を真っ直ぐ見据えて言った。
「残念ながら、彼女の胸のサイズは俺に響かん」
「……え?」
「年月というのは残酷だ。才能を伸ばしても、肉体を成長させるとは限らないのだからな」
「おまえ、結構サイテーだな……」
鷹原の蔑んだ目を尻目に、俺は自分のラケットを手にする。
かつて俺は、内気でひ弱で恥ずかしがり屋だった。
図書室に入り浸って、友と呼べるような奴もいなかった。
それでも、彼女との出会いで卓球と出会った。あの頃に比べ友達もできた。
小さなきっかけだったけど、俺にとっては、世界を変えるくらいの出来事だった。
そして、やはり初恋だったんだろう。
だから──、俺にとって卓球は特別な物のままだ。
「さて……」
俺は気を取り直して、いつものラケットを握り直す。
「今日も特訓をやるのか?」

©VisualArt's / Key